【前回記事】
前回記事では、ヘレンドがヨーロッパで知られる磁器工房になるまでをまとめました。
古くから文明が混じり合うハンガリーという地で、技術と運をものにしたヘレンドの歴史にはまだ続きがあります。
……が、その前に日本の文化も関係してくるところもあるので、その点から紹介していきます。
パリ万博とジャポニズム

1867年、フランスのパリで万国博覧会が開催されます。
この時のフランスはナポレオン3世が統治していた時代であり、前回のロンドン万博に対抗し、より多くの国や地域から産業、芸術品を呼び込んでいました。
当時の徳川幕府も招待を受けますが、開国や倒幕運動に揺れる国内においてそんな余裕はありません。
一応、日本の産業の中核をなしていた藩や商人へ万博の参加を募ったところ、すでに藩士を海外に送り出していた佐賀藩、薩摩藩と数人の商人が参加の意思を表明しました。
ヘレンドもこの万博に参加し、“インドの華”を出展します。

インドの華は、有田焼“柿右衛門”様式をアレンジした模様です。
日本の柿右衛門がインドの華と呼ばれていた理由は、アジア各国の違いが分からず、日本風の作品もインド方面のものとまとめられていたからです。
かつて日本の焼物は、東インド会社を経由してヨーロッパに輸出された経緯からそのような混同が起こってしまったようです。
しかし、この万博に日本が浮世絵や焼物をはじめとした日本の文化を伝えたことで、日本とインドの違いがはっきりと認識されます。
万博では日本の多くの展示品が賞を受賞し、これを機にヨーロッパでジャポニズムが流行していくことになります。
ヘレンドとインドの華

ヘレンドがパリ万博へ出展したインドの華は、ナポレオン3世の皇后ウジェニーの目に止まります。
ウジェニーは、ハプスブルク(オーストラリア・ハンガリーを含む)皇帝ヨーゼフ2世をもてなす晩餐会に“インドの華”を選びました。
セーブル窯など自国フランスの工房ではなく、あえてヨーゼフ2世の領地の工房を選んだという点も、ウジェニー皇后の気遣いが感じられます。
当時の上流階級の流行は皇后が決めるといっても過言ではなく、ヘレンドの名は瞬く間にセレブの間で大人気となります。

この後、フランツ・ヨーゼフ皇帝の即位25周年を記念し、1873年にウィーン万国博覧会の実施が決定。
ヘレンドは新たなる万博参加への大きな足掛かりができました。
ヘレンドとアポニー伯爵

1870年代に入ると、ヘレンドは当時の有名な政治家アルバート・アポニー伯爵から依頼が入ります。
伯爵は、突然の来賓のために急遽ディナーセットが必要でした。
しかし、ヘレンドは簡素な大量生産型ではなく、職人がひとつひとつ絵付をするため、急な依頼には対応することが困難でした。
そこでヘレンドでは、伯爵が気に入っていたインドの華をアレンジし、来賓のタイミングまでに間に合う作品を提案しました。
そこで出来上がったのが“アポニーグリーン”シリーズです。

インドの華と比較してみると、絵付けが控えめになっていることが分かります。
↓

別名ヘレンドグリーンとも言われるこの絵付けは後にベストセラーになり、今ではヘレンドを代表する作品になっています。
ウィーン万博と恐慌
1873年になるとウィーン万博が開催され、そこでもへレンドはハプスブルク家による買い上げなどがあり成功を収めます。
しかし、へレンドの栄光に陰りが見えてきました。
万博の開催と同年、オーストリア=ハンガリー帝国内では、株価の暴落によって引き起こされた大不況により、数々の企業が倒産していました。

これに伴い、高級品を買い控える動きから、ヘレンドは経営難に陥ります。
1874年8月、結局打開策も講じられないままヘレンドは経営破綻。
そのおよそ2年後に破産解除がされ、それまで経営を支えてきたモール・フィシェルはここで事実上の引退。
かねてからのビジネスパートナーであった彼の息子たちが経営権を譲り受け、ヘレンドの立て直しを図ります。
今度は中産階級をターゲットに日曜食器を作りますが、高級路線を作るためのヘレンドの工房では、市場の規模に見合ったような大量生産ができませんでした。
路線変更したことでブランドの訴求力も低下し、上流階級も離れていったことから、経営再建の試みは失敗に終わります。
フィッシェル家は、ヘレンド社を農耕商会へ売却することになりました。
1885年には、ヘレンド磁器工房株式会社が設立され、株式のおよそ3分の1をハンガリー政府が所有することになりました。
ヘレンドへの税制優遇措置や無利子のローンが認められ、ブダペスト財政界の著名な人物(銀行家ヴァール・マンモールら)が経営に携わることになりました。
伯爵らの貴族顧客層の獲得もあり、ヘレンドは再生の道を辿っていくことになりました。
……かに思えましたが、創業者の手を離れたへレンドは、経営不振だった頃と変わらず中産階級向けに製品を売るという経営方針でした。
またもや経営難に陥ったへレンドは1896年、創業者フィッシェルの孫であるファルカシュハージ・イェヌーによって買い戻されました。
イェヌーは、祖父の経営理念に立ち戻り、芸術性や技巧、職人の教育に力を入れました。
大不況の終息期でもあったことも追い風になり、ヘレンドは本当の再生に向かうことになります。
ヘレンドを支えるマスター制度
マスター制度は、15世紀南ドイツの都市で生まれた、一定の技術力を有していることを証明する制度です。
高い芸術センスと技術が求められ、合格できるのはひと握りの職人のみでした。
産業革命の波にのまれ、この制度は徐々に廃れていきましたが、ヘレンドは1826年の開窯以来190年以上もの間、マスター制度を導入し続けています。
ヘレンドのマスターペインターになるには、決められた全ての絵付けを習得する必要があります。
・東洋画

→シノワズリ、インドの華シリーズなど
・西洋風の花

→ヴィクトリアシリーズなど
・果実

→フルーツコンポジションシリーズなど
・小鳥の写実

→ロスチャイルド・バードシリーズなど
・細密画

→トゥッピー二シリーズなど
……が代表とされています。
これらの洗練された技術が、現在のヘレンドにも受け継がれながら、人々を楽しませているということが分かります。
まとめ
・パリ万博によってインドの華が大ヒット
・隆盛を極めるも、不況の煽りを受けて倒産
・経営が他者へ継がれるもヘレンド復活ならず
・フィッシェル家が買い戻し、技術力重視に原点回帰
・現在のヘレンドへ繋がっていく
以上、へレンドについての歴史でした。
日本ではマイセンなどに比べてあまり馴染みのないブランドかもしれません。
大元を辿れば他社の磁器を模倣することに始まり、技術力を高めていった結果、独自のブランドが形成されていったという経緯が見てとれます。
オリジナルを生み出すのはまずは模倣からというのもよく聞く話ですね。
産業革命が起こり大量生産が主流になる中、ヘレンドの経営方針は時代遅れとも言われていました。
しかし結局は、職人の技術を大切にして作り続けたことが、およそ200年も続く有名ブランドへと変わっていきました。
自分の強みをとことん昇華させ、降ってくる運を逃さないという点は、企業だけでなく、私たち個人にも言えることなのでしょうね。
そんな学びもあるへレンドの歴史でした。
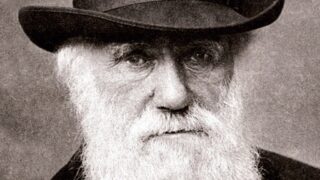
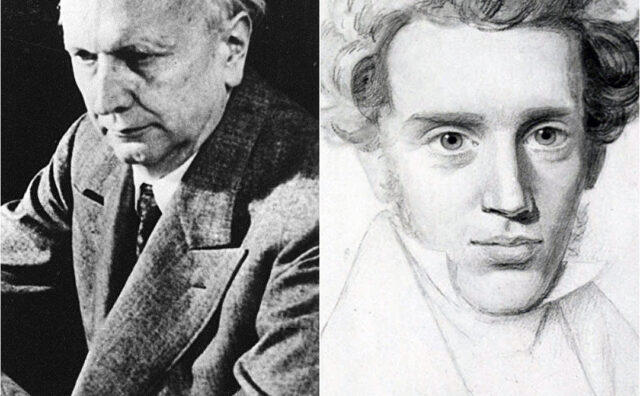
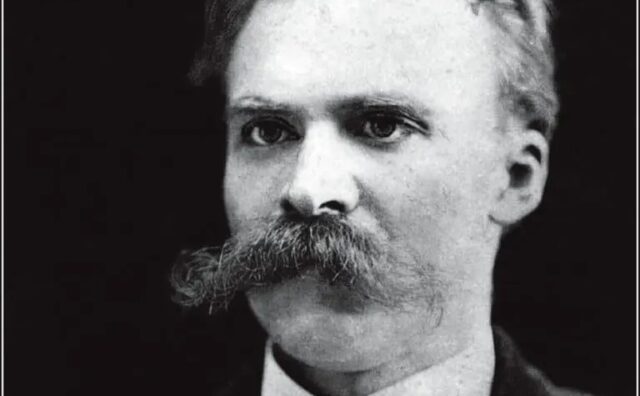



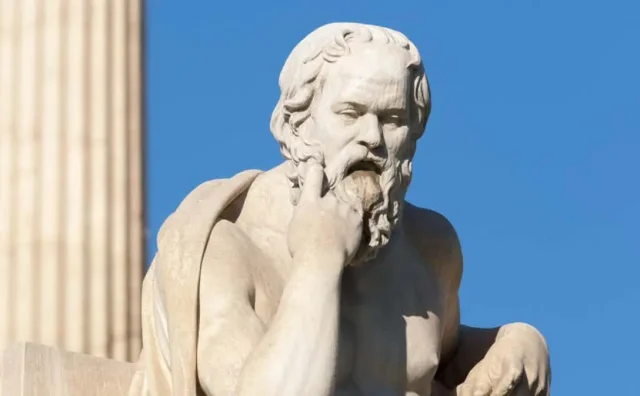



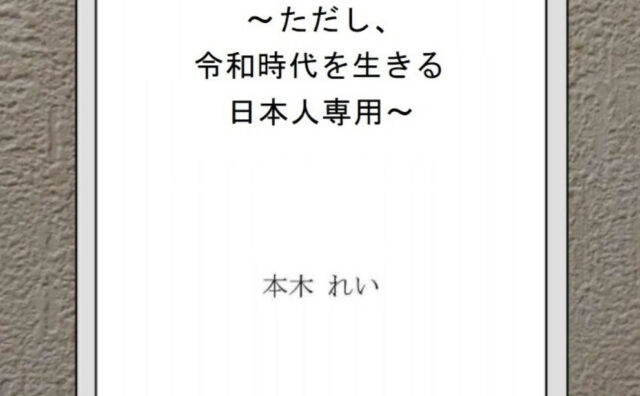





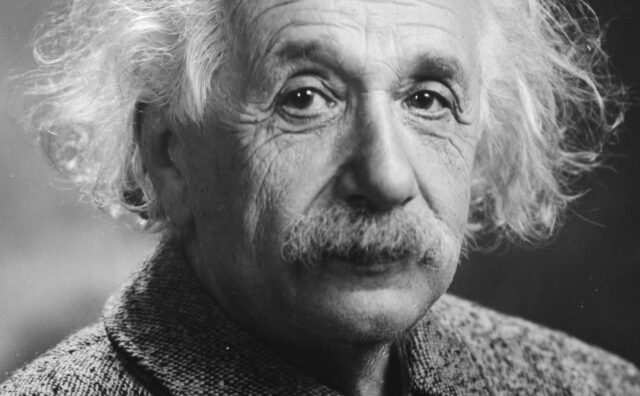


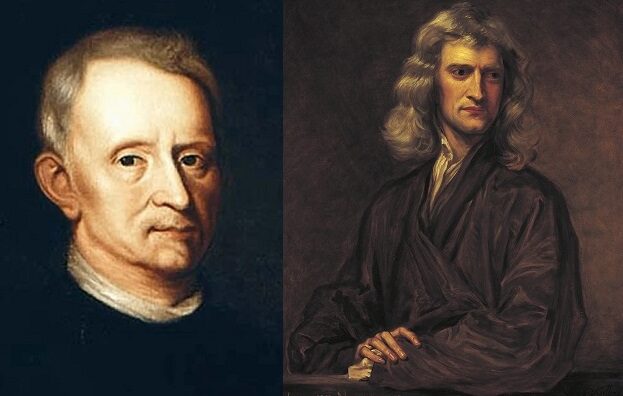



コメント