 心理学
心理学
【記事まとめ】他人も自分もコントロール~ことばの心理術~
 雑学
雑学  歴史
歴史  経済
経済  歴史
歴史  哲学
哲学  経済
経済  哲学
哲学  哲学
哲学  哲学
哲学  宗教
宗教  歴史
歴史  経済
経済 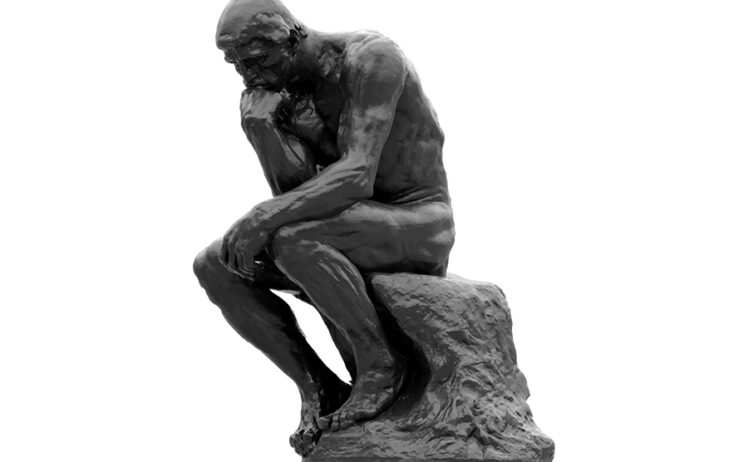 芸術
芸術  宗教
宗教  神話
神話  神話
神話  神話
神話 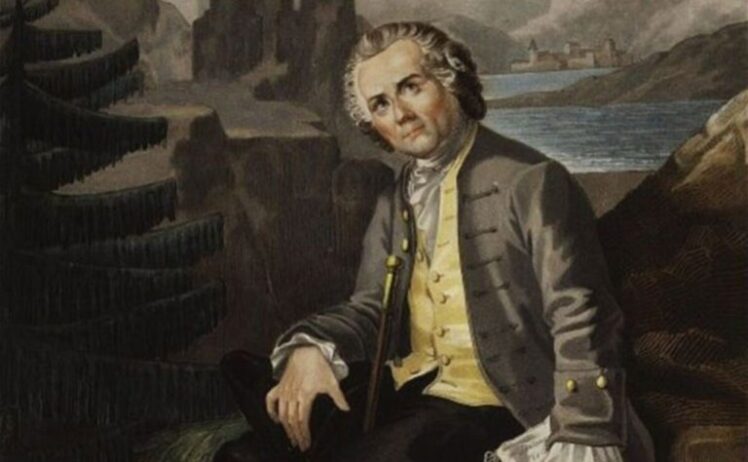 教育
教育  歴史
歴史 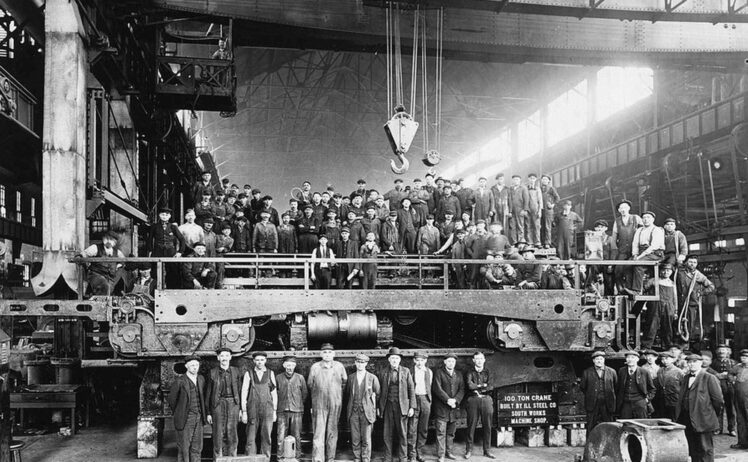 経済
経済 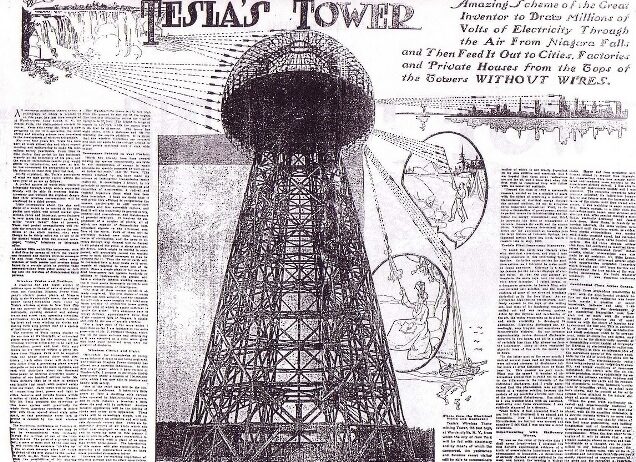 歴史
歴史 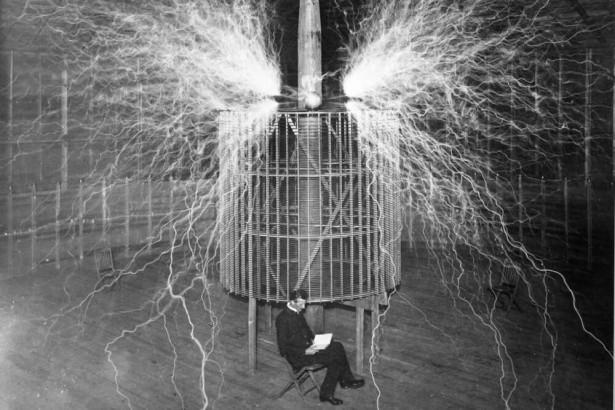 歴史
歴史 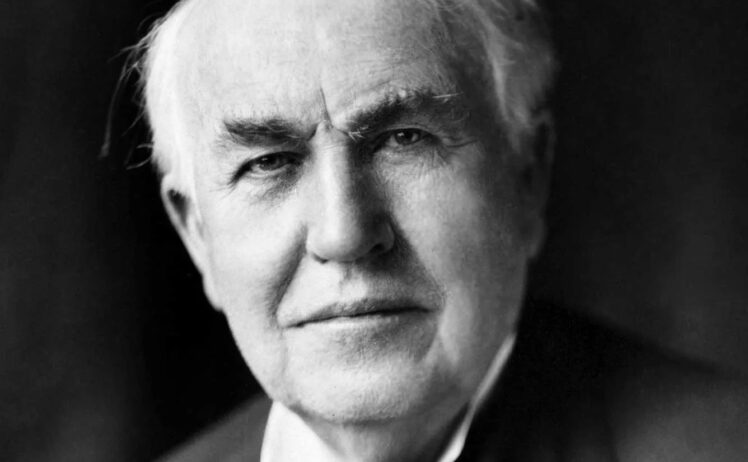 歴史
歴史 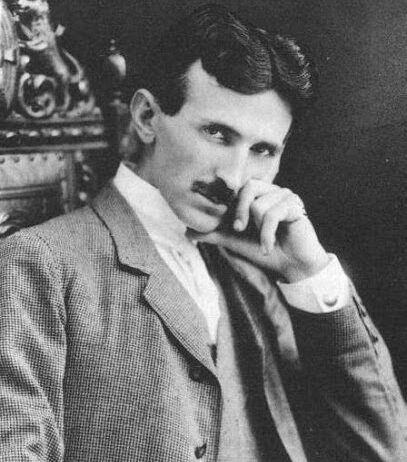 歴史
歴史 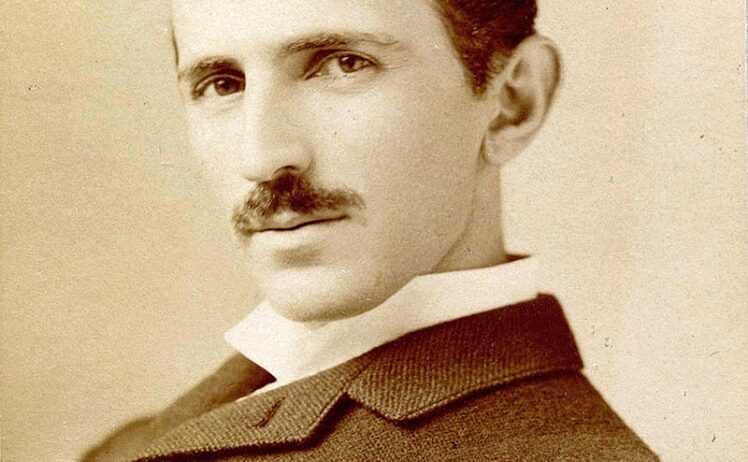 歴史
歴史 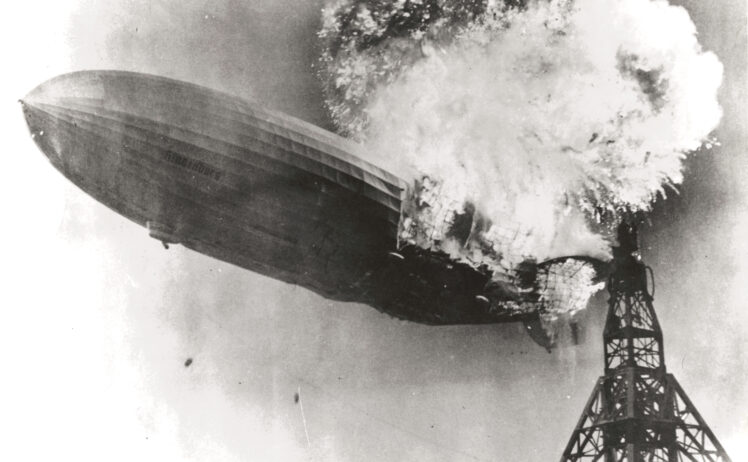 科学
科学