 雑学
雑学
【記事まとめ】日本語の雑学(全12記事)
 雑学
雑学  歴史
歴史  哲学
哲学  文学
文学  神話
神話  歴史
歴史  哲学
哲学  心理学
心理学  行動
行動  経済
経済  歴史
歴史  歴史
歴史  哲学
哲学  歴史
歴史  科学
科学  雑学
雑学  テクノロジー
テクノロジー  経済
経済  雑学
雑学  歴史
歴史 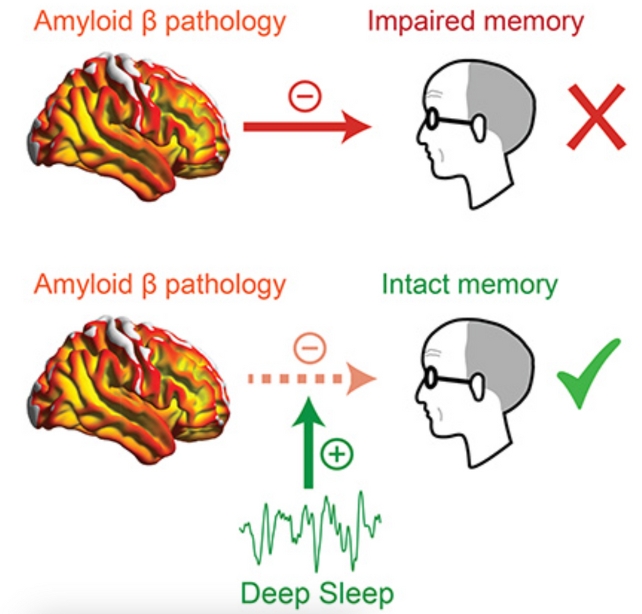 科学
科学 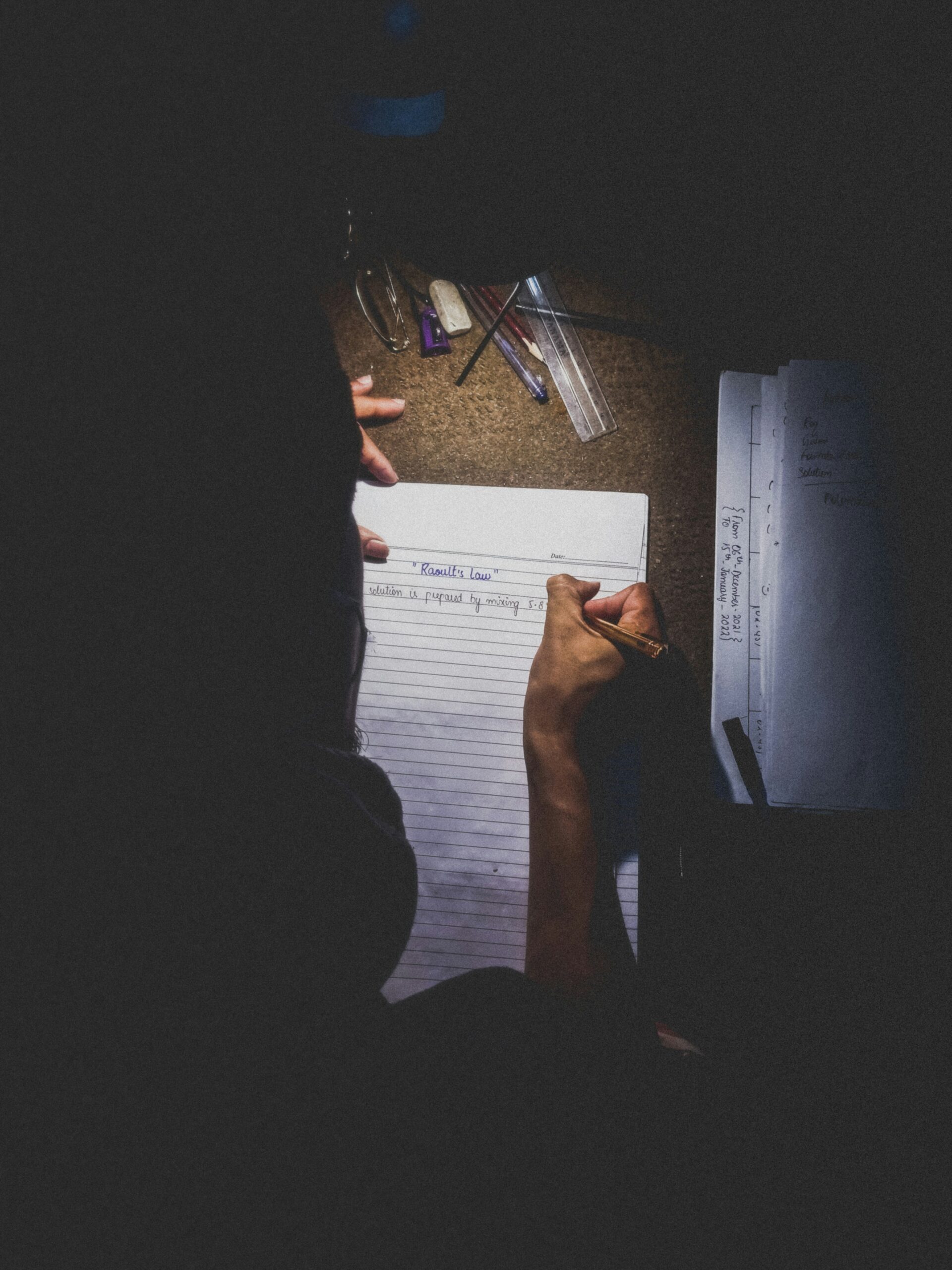 科学
科学  科学
科学  科学
科学  行動
行動  行動
行動  科学
科学  科学
科学  科学
科学  科学
科学  科学
科学 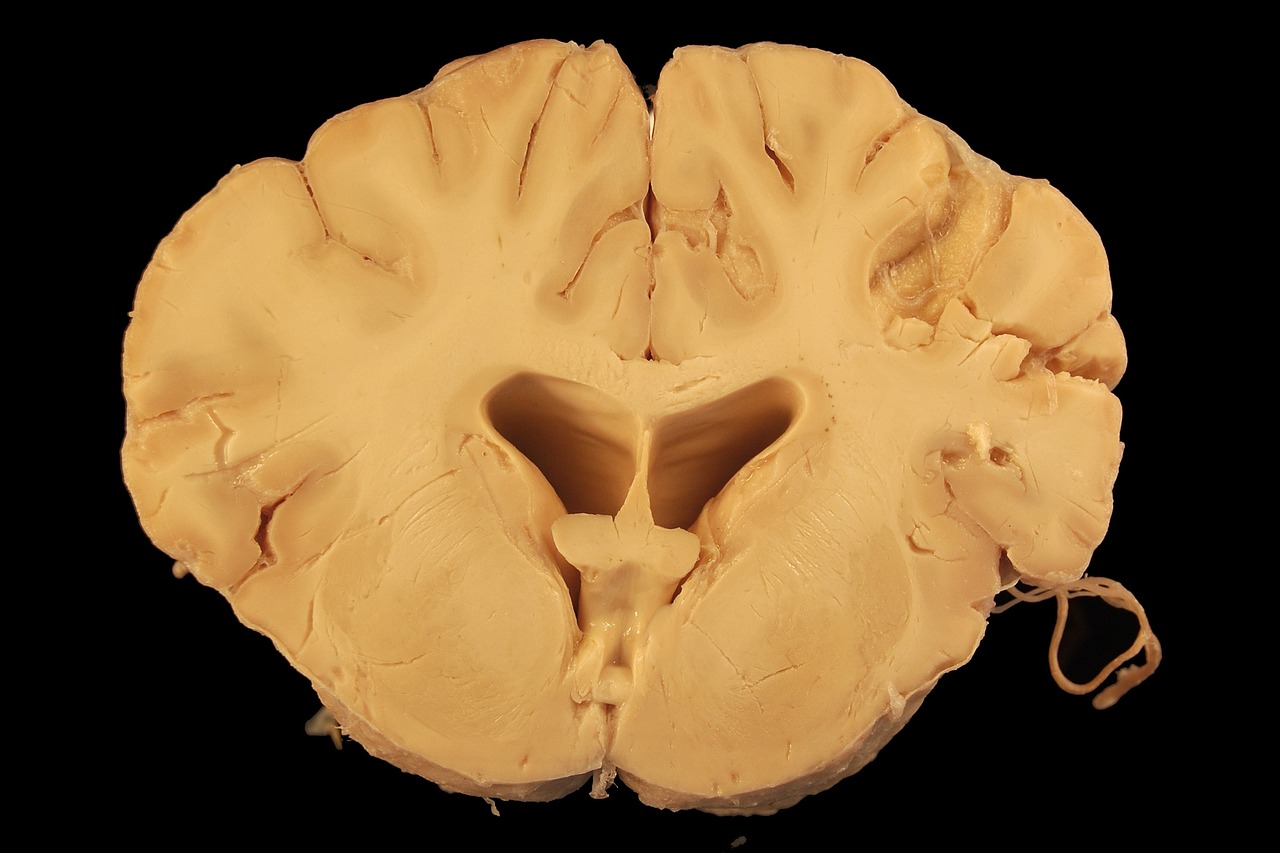 科学
科学  科学
科学  生活
生活  科学
科学  科学
科学 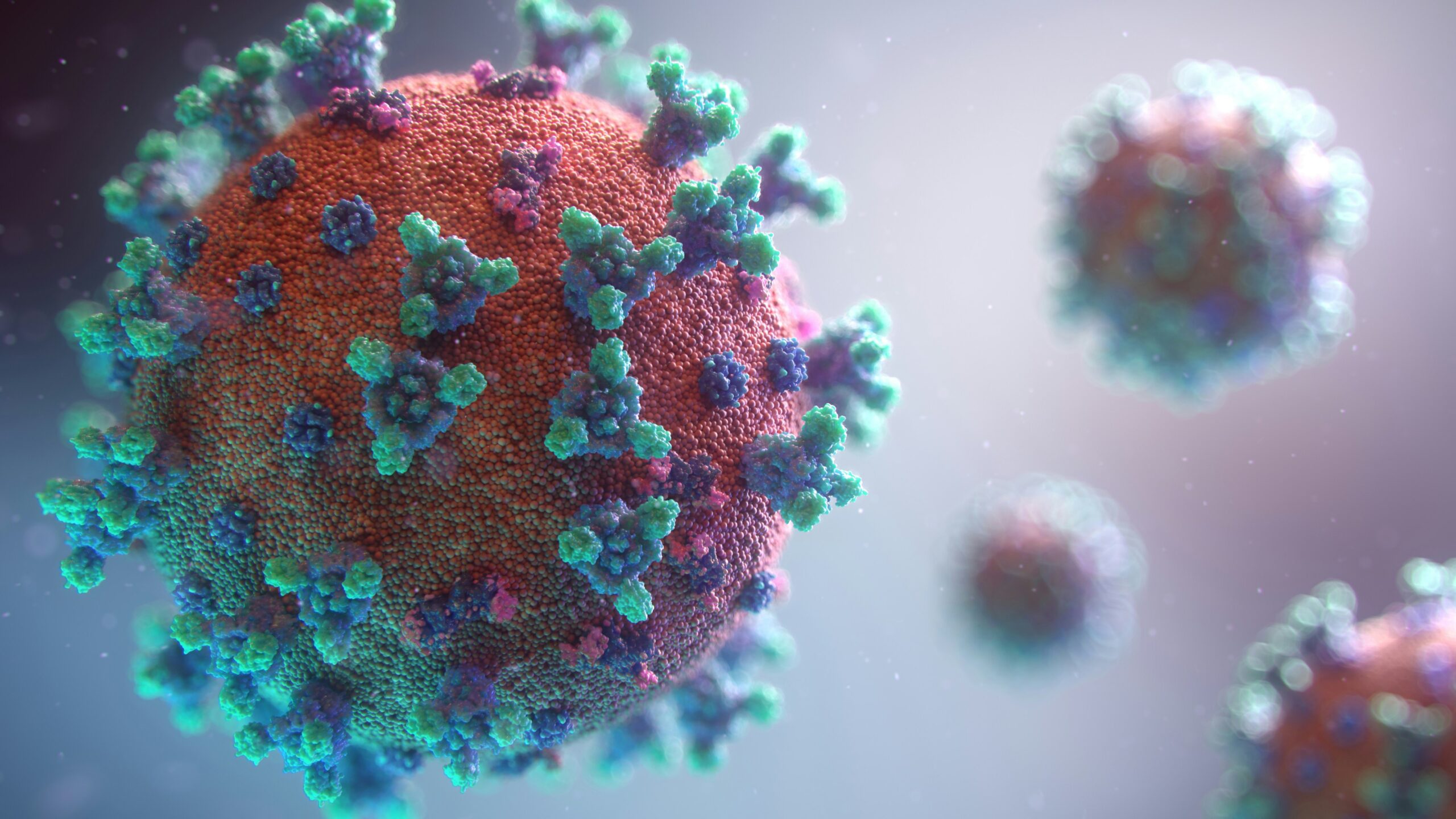 科学
科学 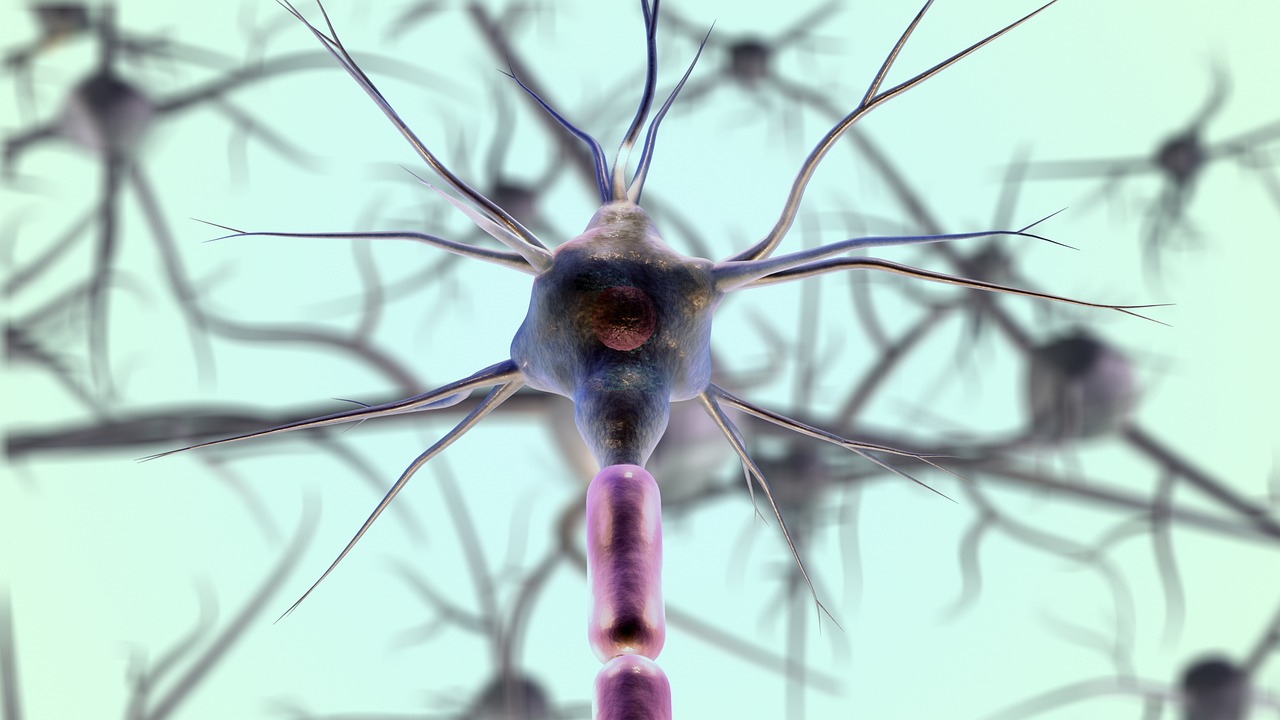 科学
科学  科学
科学  科学
科学  科学
科学  科学
科学  科学
科学  生活
生活  科学
科学 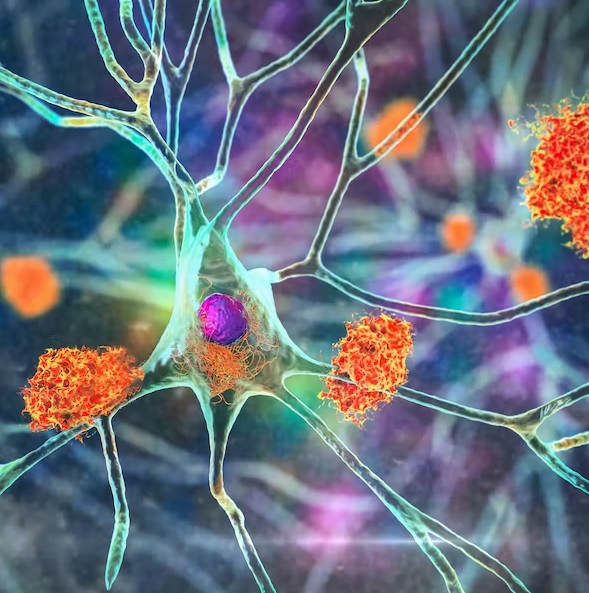 科学
科学