長年にわたり、老化に伴う慢性的な炎症(inflammaging)は避けられない現象であり、心臓病や認知症、糖尿病など、さまざまな疾患の温床になっていると考えられてきました。
つまり、年齢を重ねるごとに体内で静かに進行する免疫システムの過剰反応が、臓器や組織を徐々に摩耗させるという仮説です。
しかしながら、この「炎症性老化」がすべての人類に共通する普遍的な老化のメカニズムではない可能性を示す研究がイギリスのヨーク・セント・ジョン大学から発表されました。
最新の研究成果は、現代社会に生きる私たちのライフスタイルが、炎症性老化という現象の背景にあるのではないかという重要な示唆を与えています。
今回のテーマとして、以下に研究の内容をまとめます。
参考研究)
・Nonuniversality of inflammaging across human populations(2025/06/30)
研究の背景と目的――炎症性老化の真の姿を探る

研究チームは、老化に伴う炎症パターンの国際比較を目的とし、4つの異なる文化的背景と生活環境を持つコミュニティにおいて血中の炎症性マーカーを測定・分析しました。
調査対象となったのは以下の4つの集団です。
• イタリア人の高齢者(工業化社会)
• シンガポールの高齢者(工業化社会)
• ボリビア・アマゾン先住民のチマネ(Tsimane)族
• マレーシアの森林に暮らす先住民のオラン・アスリ(Orang Asli)
このうち前者ふたつは、いわゆる西洋型の生活を送る工業化社会に暮らす人々であり、後者ふたつは伝統的な生活様式を保持し、自然環境の中で活動的な日常を送っている人々です。
日々の活動量や食生活、自然に潜むウィルスや細菌といった、あらゆる環境が異なる集団を比べることで、近代的な老化と先住民的な老化の違いを明らかにすることが目的とされました。
「炎症性老化」は先進国特有の現象?
研究では、総勢2,800人以上の参加者から血液サンプルを採取し、サイトカイン(炎症性分子)を中心とした複数のバイオマーカーが分析されました。
特に注目されたのは、C反応性タンパク質(CRP)や腫瘍壊死因子(TNF)など、慢性炎症の進行に関与する分子です。
分析の結果、以下のような顕著な違いが明らかになりました。
【工業化社会(イタリア・シンガポール)】
• 年齢とともに炎症性マーカーが一貫して上昇
• これが慢性疾患(腎疾患・心疾患など)のリスク増加と関連していた
• この現象は従来の「炎症性老化」理論と合致するもの
【伝統社会(チマネ族・オラン・アスリ)】
• 炎症性マーカーは年齢によって一貫して上昇する傾向が見られなかった
• 年齢関連疾患(老化に伴う慢性疾患など)との相関も弱いという結果が現れた
• 特にチマネ族では、寄生虫感染や病原体への曝露が多く、慢性的に高い炎症レベルが見られた
• にもかかわらず心臓病、糖尿病、認知症などの発症率は非常に低いという事実が確認された
この結果から、研究チームは「炎症性老化は、すべての人間に共通する生物学的現象ではない可能性がある」と結論づけました。
なぜ伝統社会では老化と炎症が結びつかないのか?

この興味深い違いは、生活様式の違いからくる免疫システムの適応によって説明されるかもしれません。
伝統的な生活を送る人々は、以下のような特徴を持っています。
• 身体活動量が多い
• 加工されていない自然な食事
• 感染症や寄生虫への曝露が多い
このような環境では、炎症反応が高いこと自体が正常で健康的な適応反応であり、老化にともなう身体の崩壊を意味しないと考えられるのです。
つまり、炎症=悪ではなく、「炎症の意味と役割が環境によって変化する」という視点が必要であることが示されています。
一方で、炎症性老化がまったく存在しないのかどうかは未解明のままです。
血液中の炎症性分子だけでは捉えきれない、細胞や組織レベルでの「見えない炎症」が存在する可能性もあり、今後の研究が求められます。
本研究の意義
この研究には、医療や健康政策にとっても重要な発見です。
特に、「炎症性老化の判断基準」、「運動や食事療法、薬による介入」、「多様性を考慮する必要性」など、これまでの西洋医学からさらに進歩したアプローチを提供できる可能性が見出されます。
1. 炎症性老化の診断基準の再考
これまでの医学では、血液中の特定の炎症性マーカーを基準として、老化に関連する慢性炎症を測定・診断してきました。
しかし今回の研究結果は、この診断法がすべての人に当てはまるわけではないことを示しています。
つまり、地域や文化、生活様式によって基準を変える必要がある可能性があるのです。
2. ライフスタイル介入の効果に地域差がある可能性
運動や食事改善、特定の抗炎症薬による介入が、必ずしもすべての人に効果的であるとは限りません。
伝統的な生活を送る集団にとっては、これらの介入が不必要、あるいは効果が薄いこともあり得るのです。
3. 研究対象の多様性の必要性
現在の医療知識の大半は、工業化された裕福な国々で行われた研究に依存しています。
これは、「人類の標準的な健康像」として世界に広められてきましたが、その知見を地球規模で適用するには限界があることを、本研究は強調しています。
今後の課題と展望――見えない炎症を捉える技術へ
研究者たちは、この成果が出発点にすぎないと明言しています。
今後は、血中だけでなく、組織や細胞レベルでの炎症検出技術の開発が求められます。
また、都市部や先進国だけでなく、日本人なら日本民族の、ヨーロッパならヨーロッパ民族の…といったより多様な人類集団を対象にした包括的な研究が進められるべきです。
これまで「老化に伴う炎症」という現象は、これまで誰にでも当てはまる普遍的な真実だと考えられてきました。
しかし、そのような固定観念は、環境や文化、生活様式によって形作られる“局所的な事例”である可能性があることが、本研究によって示されたと言えるでしょう。
まとめ
・「炎症性老化」はすべての人類に共通する現象ではない可能性がある
・伝統的な生活を送る先住民では、炎症の上昇と老化・疾患リスクが一致しない
・現代医学の診断基準や介入法は、生活様式によって見直す必要がある





















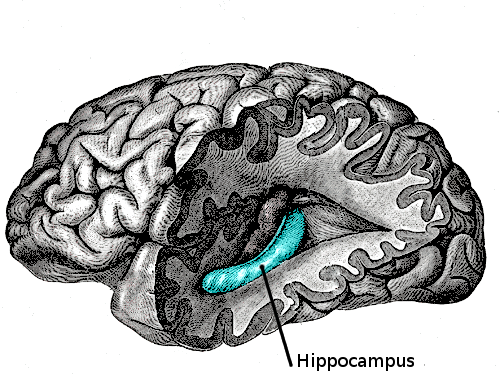

コメント