体重の増加といえば、多くの人が真っ先に「カロリーオーバー」や「運動不足」を思い浮かべるでしょう。
しかし、最新の研究はそれとは異なる新たな仮説を提案しています。それは、日常生活におけるさまざまな「生活の不安定さ(Lifestyle Instability)」こそが、年間を通じて体重が増えていく主な要因かもしれない、というものです。
イギリスのラフバラー大学に所属する運動科学者のArthur Daw氏とその研究チームは、学術誌『International Journal of Obesity』に発表した論文の中で、生活の中で起こる小さな変化やイベント、ストレスなどが積み重なることによって、私たちの体重が徐々に、あるいは急激に増えていくプロセスについて論じています。
以下の記事を参考に、今回のテーマとしてまとめていきます。
参考記事)
・Weight Gain Might Be Linked to ‘Lifestyle Instability’, Not Just Calories(2025/04/19)
参考研究)
・Lifestyle instability: an overlooked cause of population obesity?(2025/04/09)
年間を通じて体重が断続的に増える?

これまで肥満研究においては、「毎日少しだけでもカロリーを多く摂りすぎることで、年間数キロずつ体重が増加する」という理論が広く受け入れられてきました。(Adipose tissue retains an epigenetic memory of obesity after weight loss
より)
これは、例えば「毎日ブドウ数粒分のカロリーを余計に摂取するだけで、1年後には脂肪が数キロ増える」というような考え方です。
しかしDaw氏らは、この理論は実際のデータと一致しない可能性があると指摘しています。
最新の技術、たとえばFitbitのようなウェアラブルデバイスによって得られた詳細なデータを分析することで、体重の増加は実際には特定のイベントやストレスに連動する「スパイク(急増)」として現れることが多いことがわかってきました。
つまり、私たちの体重は日々少しずつではなく、生活の中で起こる非日常的な出来事や変化—たとえば病気、引っ越し、職場でのトラブル、大型連休、育児ストレスなど—によって一時的に増え、そのまま戻らないまま定着していくというパターンが多く見られるのです。(Weekly, seasonal and holiday body weight fluctuation patterns among individuals engaged in a European multi-centre behavioural weight loss maintenance interventionより)
「生活の乱れ」が引き起こす食事と運動の変化
研究では、以下のような日常生活の中でよくある「不安定要因」が体重増加に影響すると指摘されています。
• 受験や仕事による精神的ストレス
• 恋人や家族との関係トラブル
• 病気や怪我による身体的制限
• 子育てによる生活リズムの乱れ
• 抗うつ薬やホルモン療法など薬の使用
• 引っ越しや転職といったライフステージの変化
• 旅行や祝祭日など楽しいイベント
これらはすべて、食事の質・量、運動量、睡眠時間、ホルモン分泌などに直接影響を与える要素です。
特に、「楽しいイベント」に含まれるクリスマスや誕生日会、旅行での暴飲暴食なども、結果的に長期的な体重増加のきっかけになるとされています。
さらに最近の研究では、たった5日間のジャンクフードの摂取でさえ、体内で肥満を引き起こす生理的プロセス(obesogenic processes)が始まる可能性があることが報告されています。
ストレスによるホルモン反応と「甘いもの欲求」

睡眠不足や仕事の不安、鬱病や薬の影響……といった慢性的なストレスは、体にとってさまざまな悪影響を及ぼします。
そのひとつが、ホルモンの「コルチゾール」の増加です。
これは私たちの生存本能を支える重要なホルモンですが、コルチゾールが増えると、代謝は一時的に抑えられ、血糖値の乱れによって「甘いものが食べたい」という衝動が強まる傾向があります。
こうした反応は、本来「捕食者から逃げる」といった一時的な緊急事態に対応するために役立っていたものですが、現代社会では経済的なストレス、長時間労働、人間関係の悩みなど、終わりの見えない慢性的なストレスが存在します。
このため、ホルモンが過剰に作用し続け、結果的に体重増加や肥満へとつながってしまうのです。
「AI」や「外部からの一時的な介入」が効果的かもしれない
Daw氏とその研究チームは、これらの生活の乱れやストレスに対して、人工知能(AI)を活用することで、体重増加の兆候を早期に察知し、行動変容を促すことができる可能性があると提案しています。
例えば、AIが食事の傾向や運動量の減少をリアルタイムで検出し、「今日は少し外を歩いてみませんか?」といった問いかけや「最近、夜遅くに甘いものを食べていますね」といった注意喚起など、ちょっとしたことで生活習慣を整えるサポートをすることができれば、年間を通じた体重増加を防ぐ鍵になるかもしれません。
また、体重増加が「長期的なもの」ではなく「短期的なスパイク」であるならば、そういったポイントを絞った対策で十分効果がある可能性が高いと研究チームは述べています。
「体重」ではなく「健康習慣」に目を向けるべき理由
最後に、Daw氏らは私たちにこう提言しています。
体重そのものに一喜一憂するのではなく、「どれだけ健康的な食事や運動ができているか」に注目すべきだと。
なぜなら、体重という数字には遺伝や代謝、生活環境など、私たちの努力ではどうにもならない要素が多く含まれているからです。
そのため、「太ったからダメ」なのではなく、「今日は少しストレスが多かったから、早めに寝よう」「散歩してリフレッシュしよう」といった柔軟な自己ケアの習慣こそが、長期的な健康につながる鍵になると言えるでしょう。
まとめ
・体重は毎日少しずつ増えるのではなく、生活の不安定さによって断続的に増える可能性がある
・ストレスやイベントは食習慣や代謝に強く影響し、体重の「スパイク」を引き起こす
・AIや短期介入によって生活の乱れに対応すれば、体重増加の予防につながる可能性がある






















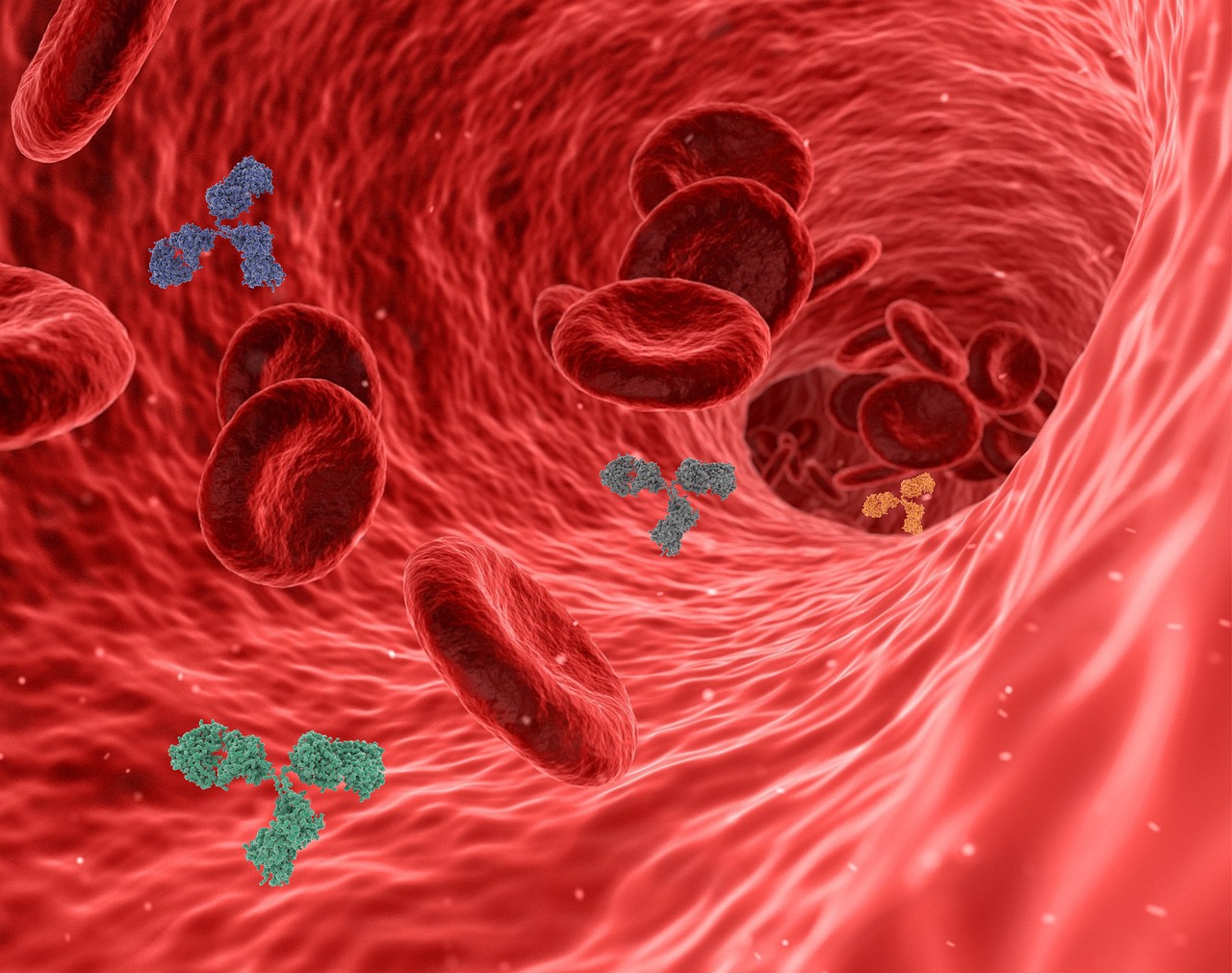
コメント