 神話
神話
【記事まとめ】エジプトの神々と死生観
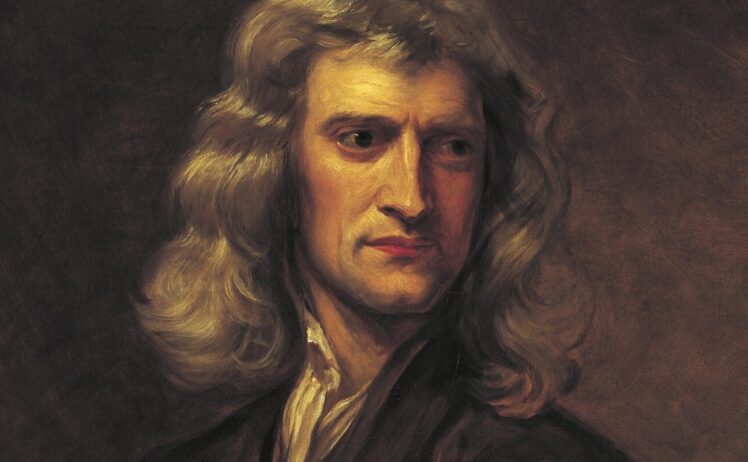 歴史
歴史  歴史
歴史 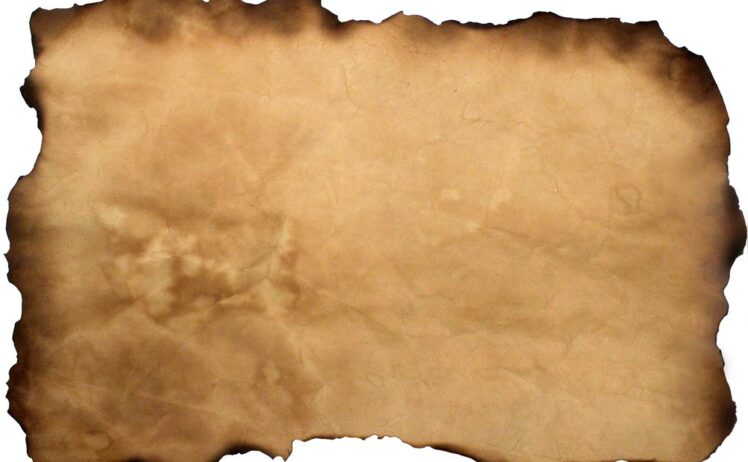 歴史
歴史 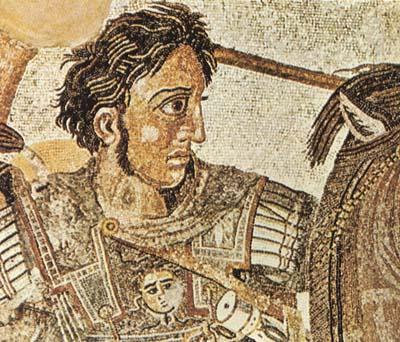 歴史
歴史  歴史
歴史  歴史
歴史  歴史
歴史  歴史
歴史  歴史
歴史 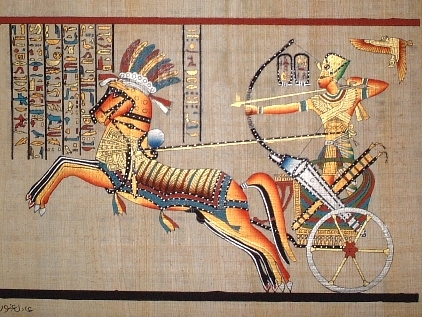 歴史
歴史 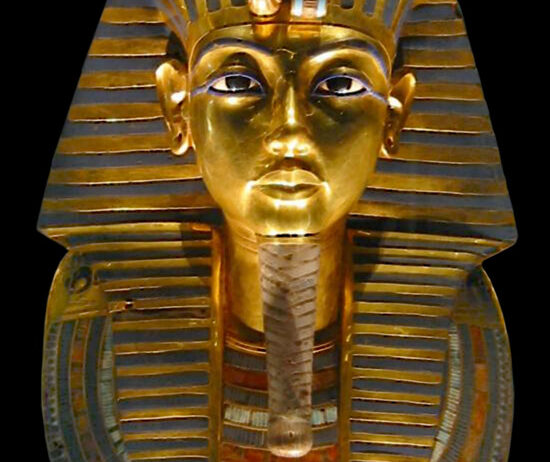 歴史
歴史 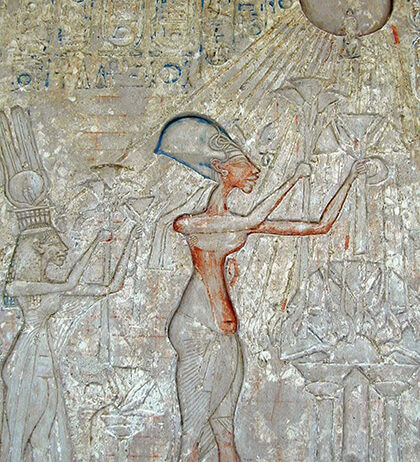 歴史
歴史 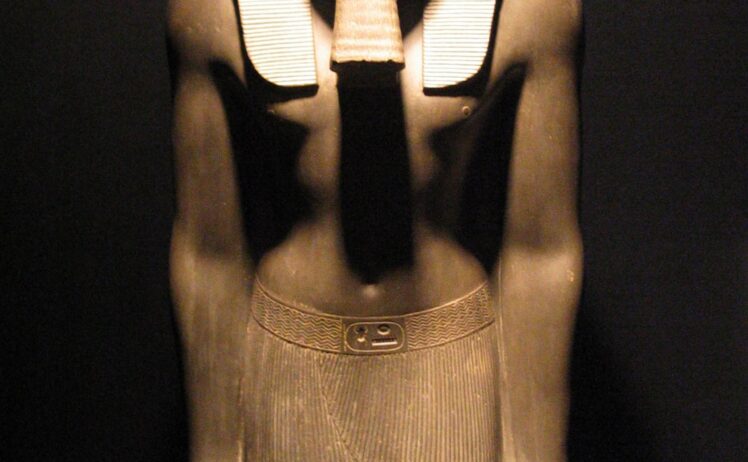 歴史
歴史  歴史
歴史  歴史
歴史  歴史
歴史 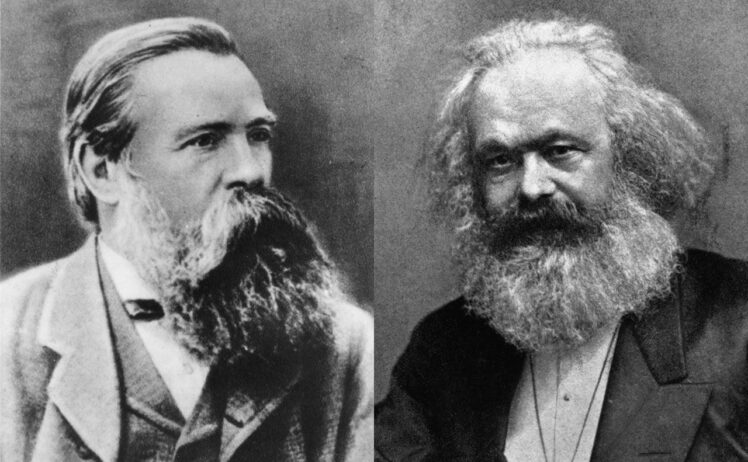 哲学
哲学 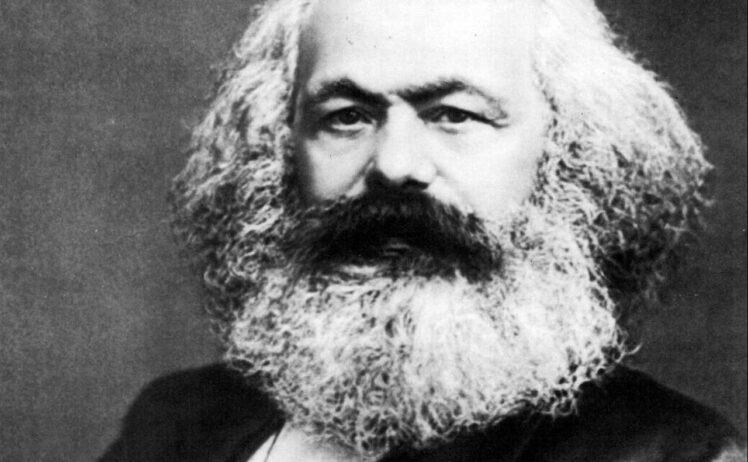 哲学
哲学 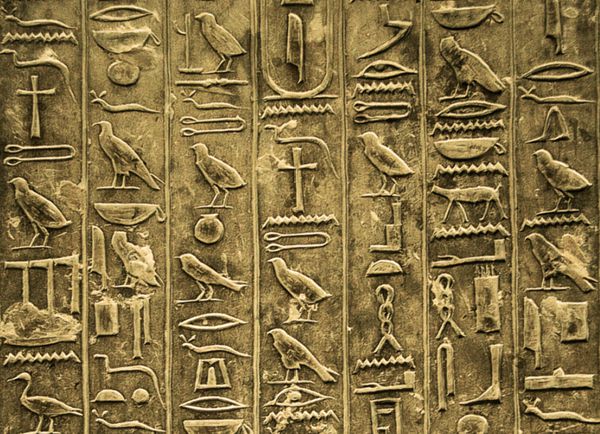 歴史
歴史  歴史
歴史  歴史
歴史 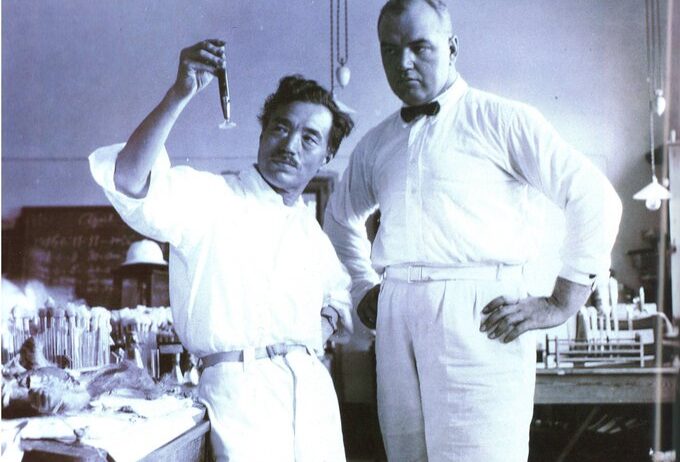 歴史
歴史 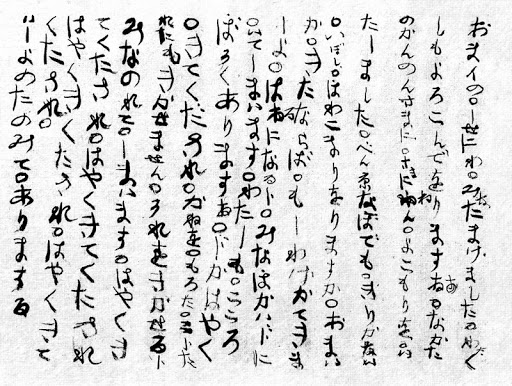 歴史
歴史 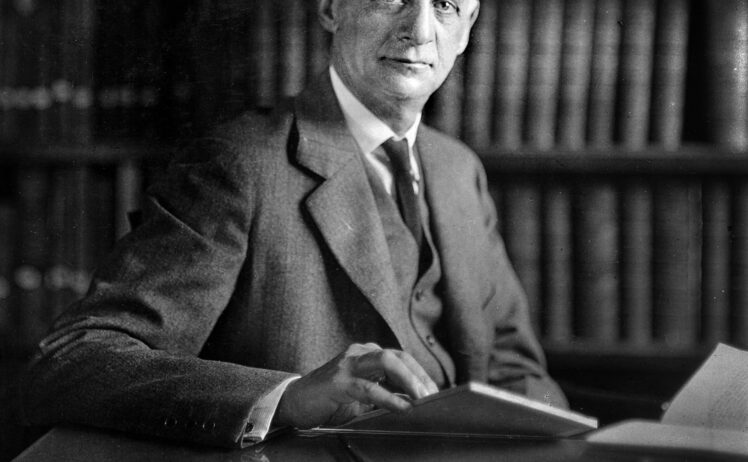 歴史
歴史 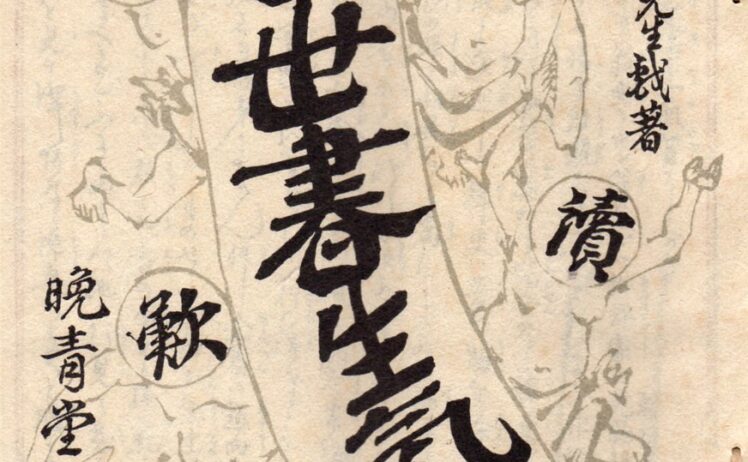 歴史
歴史 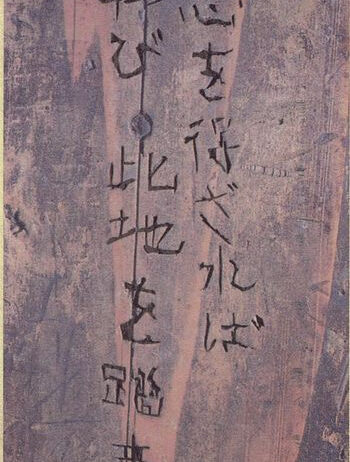 歴史
歴史