【前回記事】
この記事では、山口謠司氏が著した“面白くて眠れなくなる日本語学”より、個人的に興味深かった内容を紹介していきます。
著書内で語りきれていない点などもの補足も踏まえて説明し、より雑学チックに読めるようにまとめていく積もりです。
今回のテーマは“「ら」抜き言葉は有りか無しか”です。
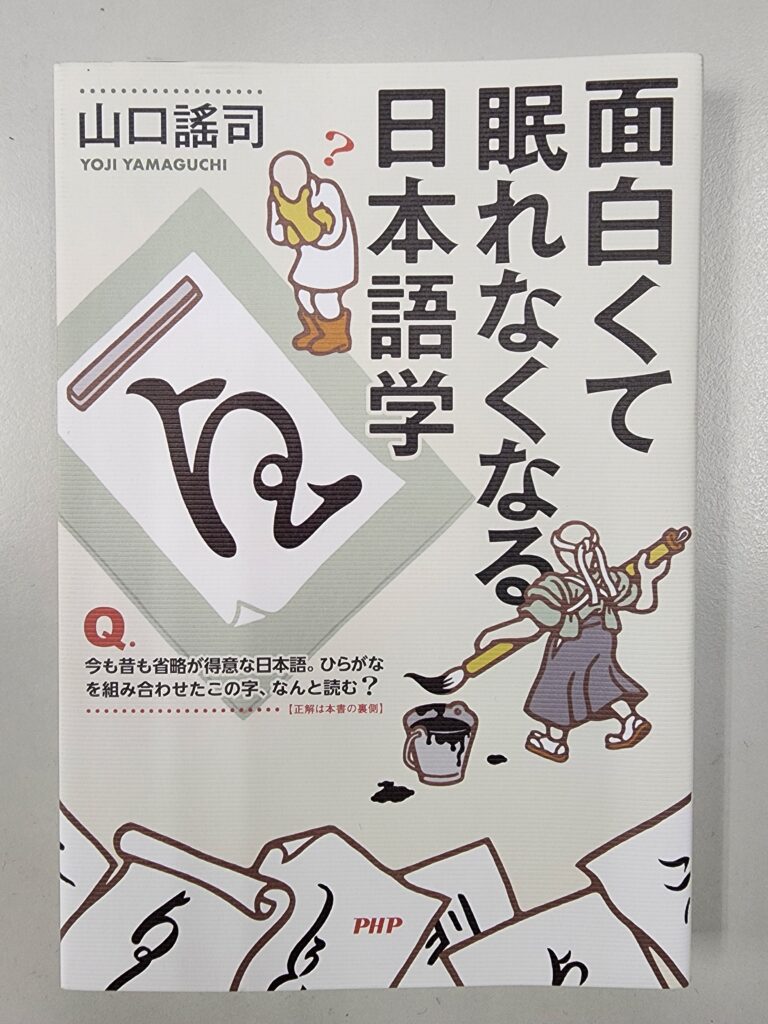
「ら」抜き言葉は有りか無しか
室町幕府3代将軍 足利義満
「来られる」が「来れる」
「見られる」が「見れる」
「出られる」が「出れる」
ら抜き言葉は、若者言葉として批判的に受け止める人もいます。
しかし、実はこのら抜き言葉の歴史を探ってみると、室町時代後期に起こる五段活用の影響があることが分かってきます。
現代日本語の「読む」は、
・読ま-ない
・読み-ます
・読む-とき
・読め-ば
・読め
・読も-う
と「まみむめも」の五段をそれぞれ使って活用します
これに対して古語は、
・読ま-ず
・読み-たり
・読む
・読む-とき
・読め-ば
・読め
と「まみむめも」の四段までしか活用しません。
この“四段活用”から“五段活用”に移行していったのが、室町時代です。
古語では、「できる」という意味を表すとき「る・らる」という助動詞を使うことができます。
現代語で言う「読む」と「できる」を組み合わせた「読める」という言葉を例にすると、古語では「読むる」、室町以降では「読まれる」となります。
しかし、「読まれる」という言葉は現代語では丁寧語の「お読みになる」の意味にあたります。
室町時代後期以降、いつしか可能を意味する「読まれる」は、「まれ」が「め」に変化し「読める」となっていったことが知られています。
そう考えると「見る」と「できる」を組み合わせた「見れる」という言葉は、古語では「見られる」と同じ形をとるので、あながち間違いでは無いということになるのです。
川端康成と「ら」抜き言葉
川端康成(1899~1972年)
室町時代後期から“受身・尊敬・可能・自発”の4種類の意味を持っていた助動詞「る・らる」は、現代日本語の「れる・られる」に変化する過程で徐々に変化していきました。
「読まれる」は「読める」
「着られる」は「着れる」
「食べられる」は「食べれる」
と変化したことによって、元々あった「読まれる」や「着られる」と言われた際、聞き手は咄嗟に尊敬か受身のどちらかと判断できるようになるのです。
室町時代後期から始まるこの言葉の変化は、京都、大阪、江戸など各都市を中心に拡大し、次第に地方に及んでいくことになります。
これが一気に広がるのは大正時代から昭和初期です。
川端康成が東京朝日新聞に連載されていた“浅草紅団”という作品では、そういった“ら抜き言葉”が頻繁に使われています。
その後にベストセラーになる“伊豆の踊子”や“雪国”などもら抜き言葉がたくさん使われています。
一説で、はら抜き言葉を全国に蔓延させたのは、川端康成の小説だったのではないかと言われるほどです。
もしこれが本当だったら、若者言葉とは見当違いなのかもしれませんね。
しかし、“ら抜き言葉”自体は、室町時代から次第に起こる日本語の変化によって生じたものということも頭に入れておかなければなりません。
一応自分も記事を書く上では“ら抜き言葉”に気をつけています。
「着れる」は「着ることができる」と書き直すことも何度もあります。
ら抜き言葉を聞くと違和感がある時がありますが、時が経つにつれて、段々とその違和感がなくなっていくのかもしれませんね。
それもた、日本語の変化なのだと思います。







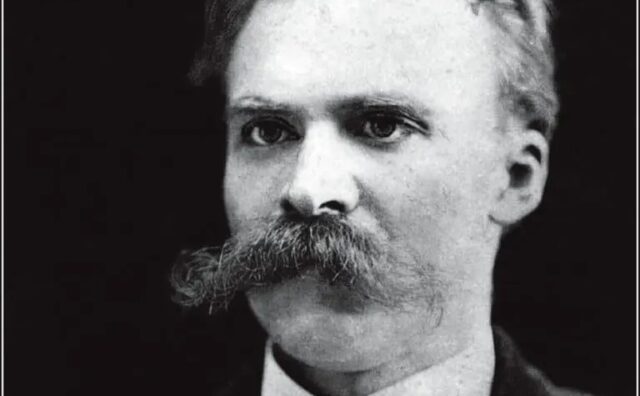




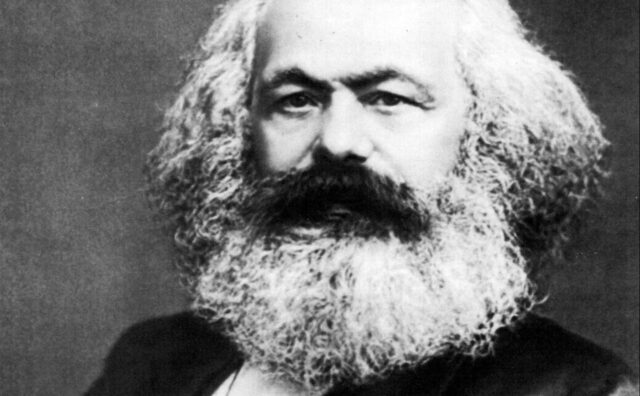




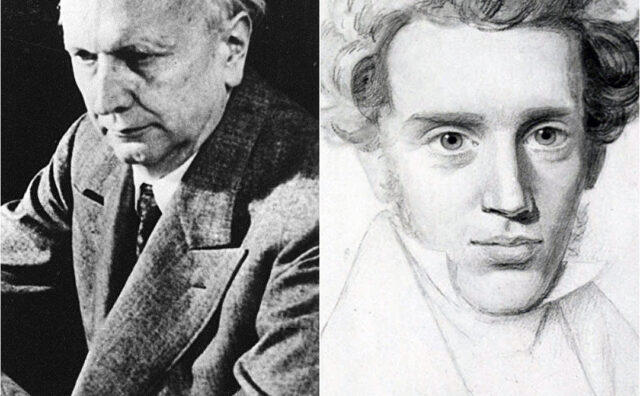

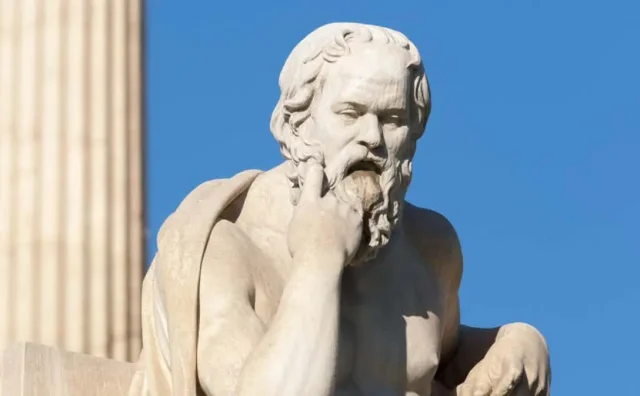






コメント