今回紹介するのは、イギリスにおける肥満対策についての取り組みです。
イギリスにおいて、肥満が原因とされる糖尿病や肝障害などの健康被害、および医療費の増大は大きな経済損失となっており、早急な改善が必要とされています。
イギリス、日本ともにBMIが30以上となると肥満と判定され、イギリスでは約28.7%が、日本では約4.9%が肥満の定義に当てはまります。
しかし、肥満率が低い日本でも、第三の糖尿病と呼ばれる認知症、アルツハイマー病の発症率はトップレベルです。
65歳以上を対象とした認知症患者の割合を例にすると、日本は12.3%(軽度認知症を除く)、イタリアは7.8%(こちらも軽度認知症を除く)となっています。
日本に次いで超高齢社会のイタリアと比べても、明らかな違いがあります。
そこで、病気の大元となる肥満に対し、制度を通して対策するという興味深い取り組みを観察・分析することは、日本の予防医療においても大きな助けになると感じたため、ここにまとめました。
個人的な興味の範囲ではありますが、以下にその内容を引用しながらまとめていきます。
参考記事)
・To Tackle Our Obesity Crisis, Experts Say Everything We Do Must Change(2025/07/13)
・National Food Strategy(2021/07/15)
参考研究)
・Social and Environmental Factors Influencing Obesity(2019/10/12)
イギリスでの肥満対策の方針

長年にわたり、肥満の人々に向けられてきたアドバイスは非常に単純なものでした。
「もっと少なく食べ、もっと動きましょう」。しかしこの言葉は、一見すると合理的に思えるものの、多くの人にとって効果的ではないばかりか、有害になり得る誤ったメッセージです。
肥満は意志の弱さではありません。
それは複雑で、慢性的かつ再発性の疾患であり、イギリスの成人のおよそ26.5%、10〜11歳の子どもの約22.1%がこの状態にあります。
最新の報告書(The economic and productivity costs of obesity and overweight in the UK)によれば、イギリスにおける過体重および肥満人口の増加に伴う経済的損失は年間1,260億ポンド(約27兆円)に上ると推計されています。
この内訳には、生活の質の低下や早期死亡による損失が714億ポンド、NHS(国民保健サービス)の治療費が126億ポンド、失業による損失が121億ポンド、非公式な介護コストが105億ポンドと含まれています。
食に関する政策を提唱する活動家や健康専門家たちは、政府に対して砂糖税の対象拡大、ジャンクフード広告の制限、超加工食品の再配合の義務化など、緊急かつ抜本的な対策を求めています。
国の経済を蝕む「肥満という病」
イギリス政府の依頼でHenry Dimblebyが執筆した独立報告書『National Food Strategy』では、「我々は国民を毒し、国家を破綻に導くような食のシステムを作り上げてしまった」と警鐘が鳴らされています。
このまま現状が続けば、肥満関連の社会的コストは2035年には年間1,500億ポンドにまで上昇すると見込まれています。
しかしながら、現在もなお多くの政策は、肥満を単なる生活習慣の問題と捉えており、個人の責任に過度に焦点を当てたままです。
現在では、肥満はただ太っているというだけでなく、多因子性の疾患であるという理解が広まっています。
これには遺伝的要因、幼少期の経験、文化的な規範、経済的困難、精神的健康、職業の種類など、さまざまな要素が関与しています。
こうした要因は、「サラダとフィットネストラッカー」で簡単に解決できるものではありません。
実は、こうした複雑な背景については2007年にイギリス政府が発表した『Foresight Report』においてすでに詳しく分析されており、現代社会の構造そのものが体重増加を促進する「肥満促進環境(obesogenic environment)」を形成していると指摘されています。
この肥満促進環境とは、高カロリー・低栄養の食品が安価で手軽に手に入り、日常生活の中から身体活動が排除されている社会構造を指します。
また、車中心の都市設計や、スクリーンの前で過ごす娯楽の時間によって、肥満が促進されるというものもその一例です。
こうした環境が全ての人に同様の影響を与えるわけではないという点にも注目が必要です。
特に経済的に困難な地域では、「フードデザート=食の砂漠(栄養価の高い食材を入手できる環境が乏しい地域)」、「不十分な公共交通機関」、「緑地の少なさ」などの条件が揃っており、肥満リスクが飛躍的に高まります。
このような環境では、体重増加は「異常な環境に対する正常な生物学的反応」であるとも言えます。
「食べる量を減らし、運動する」では足りない理由

多くの政策が依然として、「行動変容」を軸に構築されているにもかかわらず、このアプローチは限界を迎えています。
典型的なのが、カロリー制限と運動を勧める減量プログラムです。
行動変容が全く無意味であるとは言いませんが、それだけに頼ることは危険な物語を生み出します。
それはすなわち、体重管理に失敗する人々は「怠惰で意志が弱い」という偏見です。
肥満率と社会的困窮との関連性は明確であり、特に子どもの肥満率に顕著な差が出ています。
つまり、そいういった環境でしか生活できないことが、肥満の原因である可能性があるということです。(New Data Expose Depth of UK Childhood Obesity Crisisより)
しかし、多くの人が、肥満に影響を与える構造的・社会経済的要因の存在を十分に理解していません。
その結果、当事者たちは社会からの非難や羞恥心、偏見にさらされることになります。
本来あるべき肥満医療とは?
このような誤った認識や対策から脱却するために、今求められているのは、科学的知見に基づいた包括的でスティグマのない医療体制です。
肥満は、単に人が何を食べ、どれだけ運動したかという話ではありません。
生物学的要因、人生経験、そして社会が構築した環境のすべてによって形成されます。
それを「個人の失敗」として描くことは、数十年に及ぶ科学的証拠を無視するだけでなく、支援を最も必要としている人々に有害な影響を及ぼします。
そこで注目されているが、政府主導による病気の対策です。
国家食糧戦略(National Food Strategy)
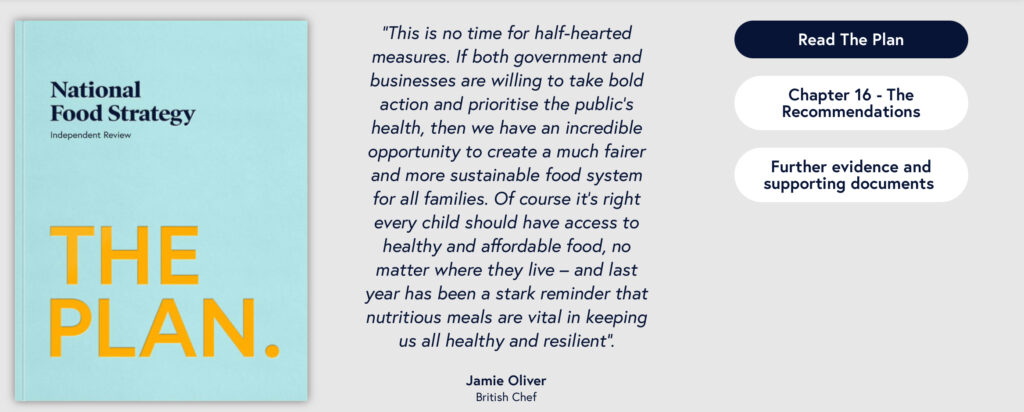
先ほど紹介した「National Food Strategy」は、2021年にイギリス政府が発表した健康増進プランです。
このプランは、今後3年間で実現可能な短期対策と、10~20年規模の構造変革を組み合わせられています。
健康・社会・環境の持続性に資する具体策が豊富に盛り込まれており、政府の支持と市民の合意形成が鍵を握る内容となっています。
戦略の基本目標
1. ジャンクフード依存を断ち切り、NHSを守る
2. 食事の格差を是正する
3. 土地・資源を最適活用する
4. 食文化を長期的に変革する
主な政策提言(全14項目のうち主要5つ)
1. 砂糖・塩に対する税(リフォーミュレーション税)
• 加工食品・外食向けに砂糖£3/kg、塩£6/kgの税を導入
• 収益は低所得家庭への果物・野菜支援に使われる
• NHS・社会福祉・経済に長期的利益(数10億~数百億ポンド規模)
2. 大企業への情報開示義務
• 従業員250名以上の企業に対し、売上構成や食品ロスなどの年次報告を義務化
3. 「Eat and Learn」プログラムの導入
• 学校を拠点とした食育拡充を推進(家庭科・調理教育の復活)
4. 「Healthy Start」や「Holiday Activities and Food」支援の強化
• 低所得家庭の子ども向けに、ホリデー期間中の食事支援プログラムとバウチャー制度を拡大
5. 1億ポンドの食イノベーション投資
• 新技術・持続可能な食体系構築に向けた国家ファンド創設(UKRI運用)
食と環境の視点
• 土地利用最適化:無駄を減らし、肉消費を30%削減すると、使用土地を1/3削減できると推計
• 自然再生と気候対策:耕作放棄地や森林再生を通じ、炭素の固定力を高める施策を提案
政策実施の意義と予測される影響
• 健康・経済効果:砂糖・塩税によるQALYsの改善とともに、NHS負担の軽減や社会インフラの健全化が期待される
• 社会的格差・健康不平等の改善:弱者支援策や食育により、長期的に医療負担を軽減し所得格差を縮小
• 食文化の再評価と技術革新:政策と資金投入により、伝統的調理スキルや持続可能性を重視した消費行動の変化を促進
課題
• 政治的抵抗:特に食品産業からの反発、政府による税制導入への慎重姿勢が大きな論点
• 実現と法的枠組みの整備:「健康・持続可能な食品法(Good Food Bill)」の成立など、データ収集・目標設定・監視・透明性のある制度設計が不可欠
タバコ税の導入と、社会的なモラルが変わったことでタバコの消費が抑えられたことや、飲酒運転の罰則が厳罰化されたことで、そのような行為が起こりにくくなったこと……。
制度によって消費をコントロールし、その結果として健康の増進や事故(または犯罪)が減るというのなら、非常に合理的であはないでしょうか。
個人的には病気の大元は「食」にあると考えているので、砂糖への税金やジャンクフードの規制などは大賛成です。
イギリスの今後を見てどのような変化があったのか……。
この取り組みが良いにしろ悪いにしろ、国民の健康のみならず、国家財政への影響についても良い目安になるはずです。
まとめ
・イギリスでの肥満による健康及び経済損失は深刻
・肥満は意志の弱さではなく、多因子的な慢性疾患
・体重差別をなくし、包括的かつ個別化された医療が求められている























コメント