私たちはそれぞれ、朝早く起きて活動する「朝型(early bird)」と、夜遅くまで起きていることが多い「夜型(night owl)」という、生物学的な睡眠の傾向を持っているとされています。
オランダのフローニンゲン大学の研究チームが主導した研究報告から、こういった個人差は単なる生活リズムの違いにとどまらず、脳の健康や老化のプロセスにまで影響を及ぼす可能性があることが示されました。
この研究は、40歳以上の23,798人を対象とした公衆衛生データを基に、睡眠習慣と認知機能検査「Ruff Figural Fluency Test(RFFT)」によるスコアを10年間にわたって追跡し、特に大学教育を受けた人々におけるクロノタイプと認知機能の関係性が詳しく調査されました。
その結果、高学歴の夜型の人々は、より速いペースで認知機能が低下する傾向があることが明らかになりました。
以下に研究の内容をまとめます。
参考記事)
・Night Owls May Be at Higher Risk of Cognitive Decline. Here’s Why.(2025/06/04)
参考研究)
高学歴かつ夜型だとリスク要因に?
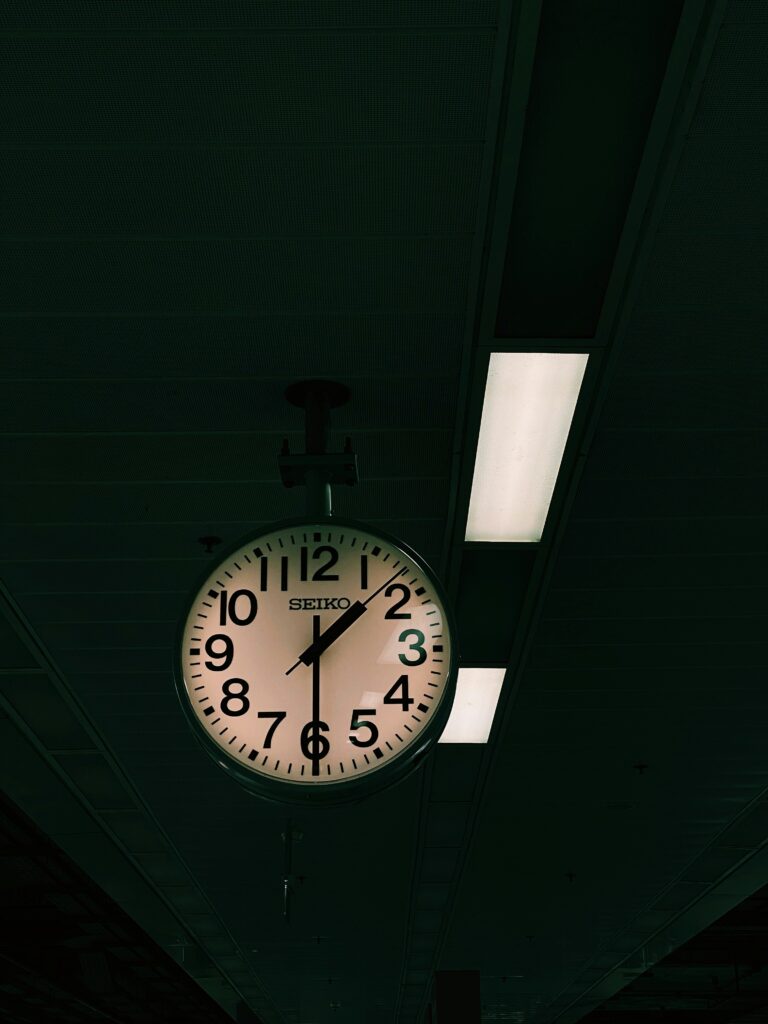
研究チームは、「夜型」であるほど認知機能の低下リスクが上がることを統計的に示しましたが、この傾向が特に顕著だったのが、高等教育を受けた層でした。
研究では、「高学歴グループでは、クロノタイプが1時間遅くなるごとに、10年間で平均0.80ポイントの認知機能の低下が見られた」と報告されています。
この「0.80ポイント」という数値は一見小さく思えるかもしれませんが、数年単位で蓄積されていけば、認知機能にかなりの影響を与えることが考えられます。
この現象について、研究者たちはいくつかの要因を仮定しています。
特に注目されたのは、睡眠の質と喫煙習慣です。
研究では、睡眠の質が13.52%、現在喫煙していることが18.64%、クロノタイプと認知機能の関連に対する媒介要因であるとされました。
これはつまり、「夜型」の人が認知機能の低下を経験する際、睡眠の質と喫煙の有無が一定の影響を与えていることを意味しています。
しかしながら、研究チームは「これらの要因が与える影響は限定的であり、全体的なリスクの一部に過ぎない」と指摘しており、他にも関連する要因があると示唆しています。
クロノタイプと認知機能の因果関係は?
本研究は大規模な調査である一方で、あくまでも相関関係を示すものであり、直接的な因果関係を証明するものではないことも明記されています。
なぜなら、生活習慣や遺伝的背景、社会環境など、さまざまな変数が影響しているためです。
そのため、たとえ夜型であっても、それ自体が必ずしも認知機能の低下を招くとは限らない点には注意が必要です。
研究では、身体活動の頻度や過去の喫煙歴、アルコール摂取量などの要因も統計的に考慮されたうえで、「それらはクロノタイプと認知機能の関連を説明する要因ではなかった」とされています。
さらに、学歴が低い、あるいは中程度のグループにおいては、有意な影響が観察されなかったという結果も得られました。
つまり、「夜型」と「認知機能の低下」との関係は、教育水準との複雑な相互作用のなかで成立している可能性があるのです。
なぜ高学歴の夜型の人ほど影響を受けるのか?
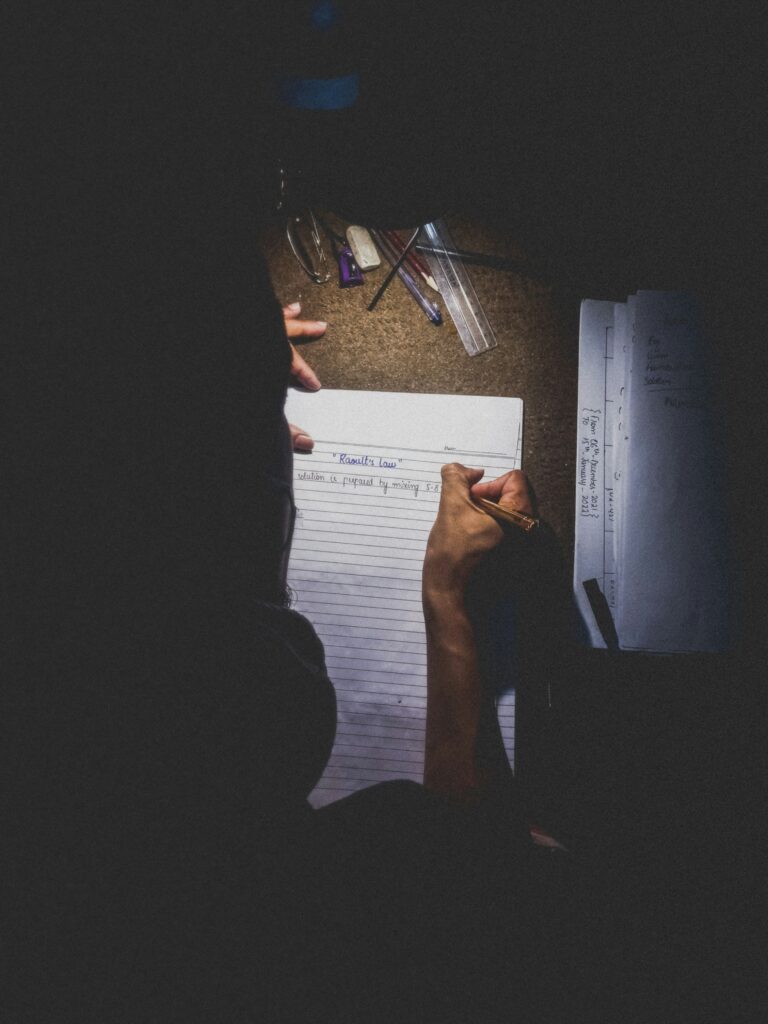
この興味深い相関関係について、研究者たちはいくつかの仮説を提示しています。
ひとつは、高学歴の人々の多くが「定時で規則正しい勤務時間」を持つ職に就いている可能性です。
つまり、夜型の傾向があるにもかかわらず、早朝からの勤務に従事する必要があるため、慢性的な睡眠不足に陥るリスク が高いのです。
また、認知機能が元々高い人ほど、その低下が統計的に顕著に現れるという「天井効果」的な側面も指摘されています。
つまり、ベースラインが高い人ほど、微細な低下でも目立ちやすくなるというわけです。
加えて、調査対象における「朝型」の人のサンプル数が比較的少なかったことも、今回の結果に一定の影響を及ぼしている可能性があると研究者は述べています。
世界的な課題としての認知症対策
現在、世界では約5,700万人が認知症を患っていると推定されていますが、2050年までにその数は1億5,000万人に達する可能性があるとも言われています。
このような背景から、認知機能の低下を早期に発見し、予防するための研究は国際的な課題とされており、本研究はその重要な一歩となるものです。
研究チームは論文のなかで次のようにまとめています。
「世界的に平均寿命が延び、高齢人口が増加するなかで、認知機能を維持することは喫緊の課題である」
このコメントは、ただの学術的な結論ではなく、社会全体で睡眠の質や生活リズムの重要性を見直す必要があるという、実践的なメッセージとも受け取ることができます。
今後の研究と実生活への応用
本研究が示したような「夜型と高学歴による認知機能の低下リスク」という知見は、今後の生活習慣改善や職場の健康管理に大きく貢献する可能性があります。
たとえば、夜型の傾向が強い人は、無理に朝型の生活リズムを維持しようとせず、フレックスタイム制度や在宅勤務を活用することで、健康リスクを減らすことができるかもしれません。
また、日常的な生活のなかで睡眠の質を向上させる工夫(光の調整、就寝前のスクリーン制限、リラックス習慣の導入など)を取り入れることは、誰にとっても有益です。
まとめ
・夜型の高学歴者は、10年間で認知機能が顕著に低下するリスクがあると示された
・睡眠の質と喫煙は関連要因だが、影響は限定的
・定時勤務と夜型傾向のミスマッチが主な原因の可能性がある




















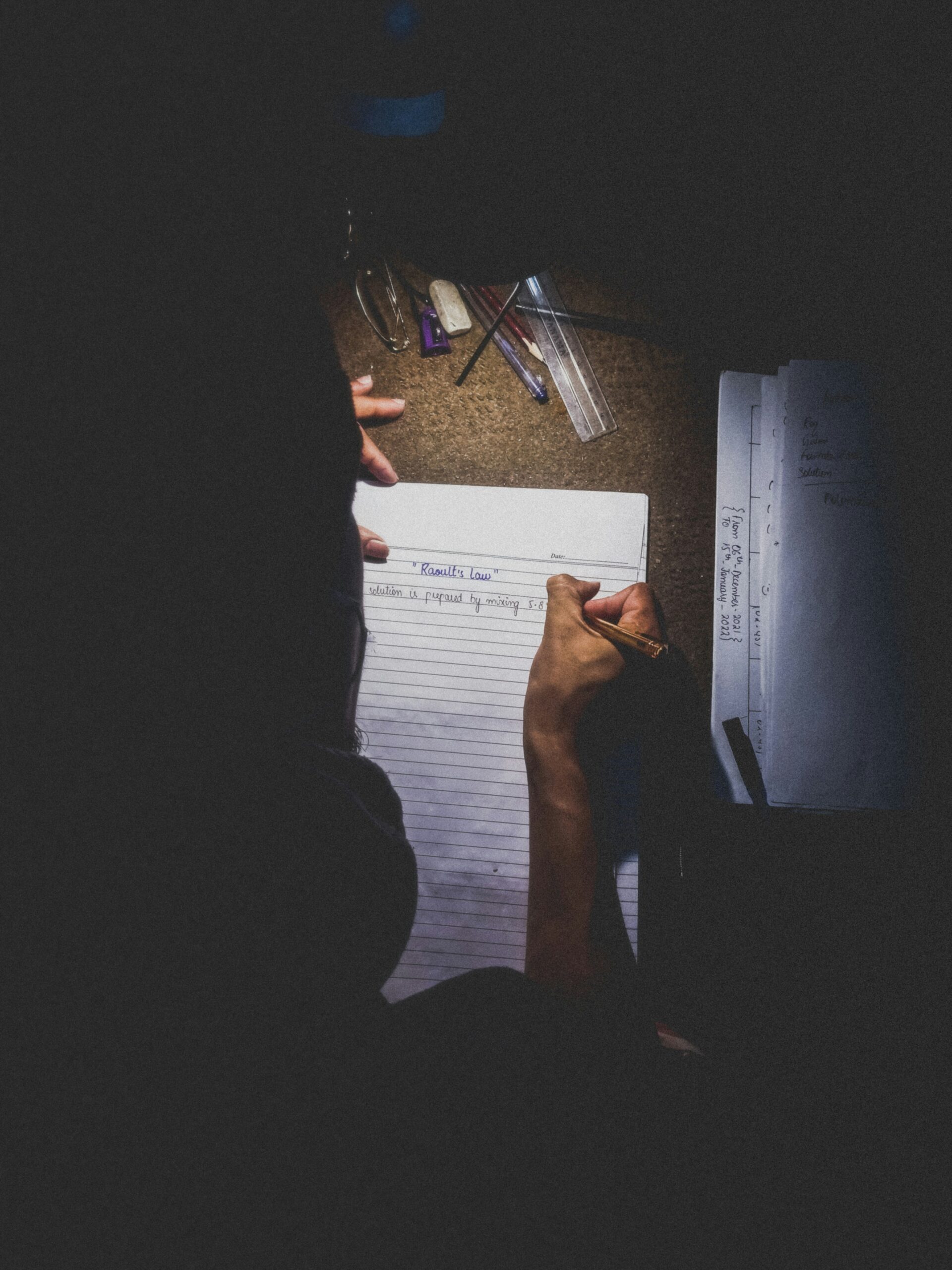


コメント