寝る時にベッドの中でスマホを操作しているとついつい夜更かししてしまう……、といった経験は誰しもあるでしょう。
時には仕事のメールに返信したり、時には好きな動画を「もう少しだけ」と使用し続けてしまうこともあるでしょう。
そういった夜を過ごした翌朝、目覚めたときに感じるのは眠気と苛立ち。
そして、いつもの朝食よりも、甘いパン菓子や脂っこいサンドイッチが妙に魅力的に見えてしまうと言う経験がある人も少なくありません。
こうした行動は、単なる「意志の弱さ」で片づけられるものではありません。
実は、脳が「休息不足」の状態にあると、高カロリーな食べ物を欲するように誘導される仕組みが働いてしまうと言われています。
最新の研究によれば、たった一晩の睡眠不足でも、食欲を制御するホルモンバランスを乱し、自制心を低下させ、糖代謝を悪化させ、さらには体重増加のリスクを高めることが分かっています。
本記事では、ピッツバーグ大学で睡眠と健康を専門としているJoanna Fong-Isariyawongse氏の研究を基に、睡眠不足がどのように私たちの「食欲」と「脳の判断」に影響を与えるのかを紹介します。
参考記事)
・Sleep loss rewires the brain for cravings and weight gain – a neurologist explains the science behind the cycle(2025/06/17)
参考研究)
・Sleep influences on obesity, insulin resistance, and risk of type 2 diabetes(2018/03/03)
睡眠不足が及ぼす影響はすぐに現れる

アメリカ疾病予防管理センター(CDC)のデータによれば、アメリカの成人の3人に1人以上が、1晩7時間未満の睡眠しか取れていないことが報告されています。
また、高校生や中高生の約75%は、平日8〜10時間の推奨睡眠時間に届いていません。
特に夜勤や交代制勤務が日常の医療従事者、消防士、救急隊員といった社会生活の維持に不可欠な仕事に携わる人々たちは、こうした睡眠不足の影響を大きく受けやすい状況にあります。
彼らの勤務スケジュールは体内時計を乱し、食欲のコントロールを難しくし、肥満や代謝性疾患のリスクを高める原因になります。
しかし、良質な睡眠を2〜3晩継続するだけでも、ホルモンバランスや代謝機能を回復させ、悪影響を逆転させる兆しが現れることも分かっています。
食欲ホルモンのバランスが崩れる

私たちの体は、「空腹」と「満腹」の感覚をホルモンによるフィードバック機構で調整しています。
ここで重要なのが、「グレリン」と「レプチン」という2種類のホルモンです。
• グレリン: 胃で作られ、「空腹」と脳に伝える役割を果たす
• レプチン: 脂肪細胞から分泌され、「満腹」と脳に知らせる役割を担う
たった一晩の睡眠不足でも、グレリンの分泌量は増加し、レプチンの分泌量は減少することが明らかになっています。
つまり、睡眠をしっかり取らなかっただけで、私たちは「いつもより空腹を感じやすく、食べても満たされにくくなる」状態になってしまうのです。
さらに睡眠不足は、満腹感に対する脳の反応を鈍らせ、ストレスホルモン(特にコルチゾール)の分泌を増加させるため、食欲をより強く刺激することになります。
実験室での研究では、健康な成人を対象に4〜5時間の短時間睡眠を与えた結果、食欲が顕著に増加し、高カロリー食品への強い渇望を訴える傾向が確認されています。
これが習慣化すれば、慢性的に過剰な食欲を持つ状態へと進行してしまうのです。
脳の「報酬系」が過剰に反応するようになる

睡眠が不足すると、脳の働き方そのものが変化します。
特に変化が顕著なのが、前頭前野(判断力や自制心を司る領域)と扁桃体・側坐核(報酬や欲求を司る領域)の活動バランスです。
画像診断研究によると、睡眠不足の状態では前頭前野の活動が低下する一方で、扁桃体や側坐核の活動は高まることが分かっています。
この結果、高カロリーな食品やジャンクフードに対して過敏に反応するようになり、脳が「報酬」としてそれを求めてしまうようになるのです。
つまり、睡眠不足の脳は「誘惑に弱くなり、我慢する力が落ちる」という、まさに「食べたくなる脳」に切り替わってしまうわけです。
実験参加者は、実際に空腹かどうかにかかわらず、カロリーの高い食品を「より魅力的」と感じ、「実際に選ぶ」傾向を見せることが繰り返し報告されています。
代謝が低下し、脂肪が蓄積されやすくなる
睡眠は、血糖値のコントロールにも欠かせません。
十分な睡眠をとった状態では、インスリンが正常に働き、血中の糖分を細胞へと効率的に運びます。
しかし睡眠不足になると、インスリン感受性が最大で25%も低下することが分かっています。
つまり、血糖がうまく処理されなくなり、余分な糖が体脂肪として蓄積されやすくなるのです。
特にお腹周りに脂肪が集中しやすくなり、糖尿病やメタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満、高血圧、高血糖などを含む症候群)のリスクが高まります。
加えて、睡眠不足によってストレスホルモンのコルチゾールの分泌が増えることも、内臓脂肪の蓄積と強く関係しています。
つまり、睡眠不足は、代謝、食欲、脂肪蓄積のすべてにおいて悪循環を引き起こすリスク要因となるのです。
睡眠は「代謝のリセットボタン」
現代社会では、「寝ないで働く」ことが賞賛されたり、「短眠」が凄いことのように扱われることがあります。
しかし、身体にとって睡眠は単なる休息ではなく、「能動的な修復と調整の時間」なのです。
睡眠中には、脳が「食欲と報酬」の神経回路をリセットし、ホルモンバランスを調整し、代謝を安定させる重要なプロセスが進行しています。
ありがたいことに、良質な睡眠を1〜2晩しっかり取るだけでも、以前の睡眠不足による悪影響を軽減し、身体のバランスを回復させることができます。
短い睡眠の翌朝に、「なぜこんなに食べたいのだろう」と感じたとき、それは意志の問題ではなく、生理的反応として起こっているのです。
そのときこそ、カフェインやダイエットに頼るのではなく、本当に必要なのは「睡眠」だと気づくことが大切です。
睡眠は贅沢品ではなく、最も効果的な「食欲コントロール」と「健康維持」のための武器なのです。
まとめ
・たった一晩の睡眠不足でも、空腹ホルモンのバランスが崩れ、食欲が増加する
・脳の報酬系が過敏になり、高カロリー食品を選びやすくなる
・睡眠不足は代謝を低下させ、脂肪の蓄積や生活習慣病のリスクを高める





















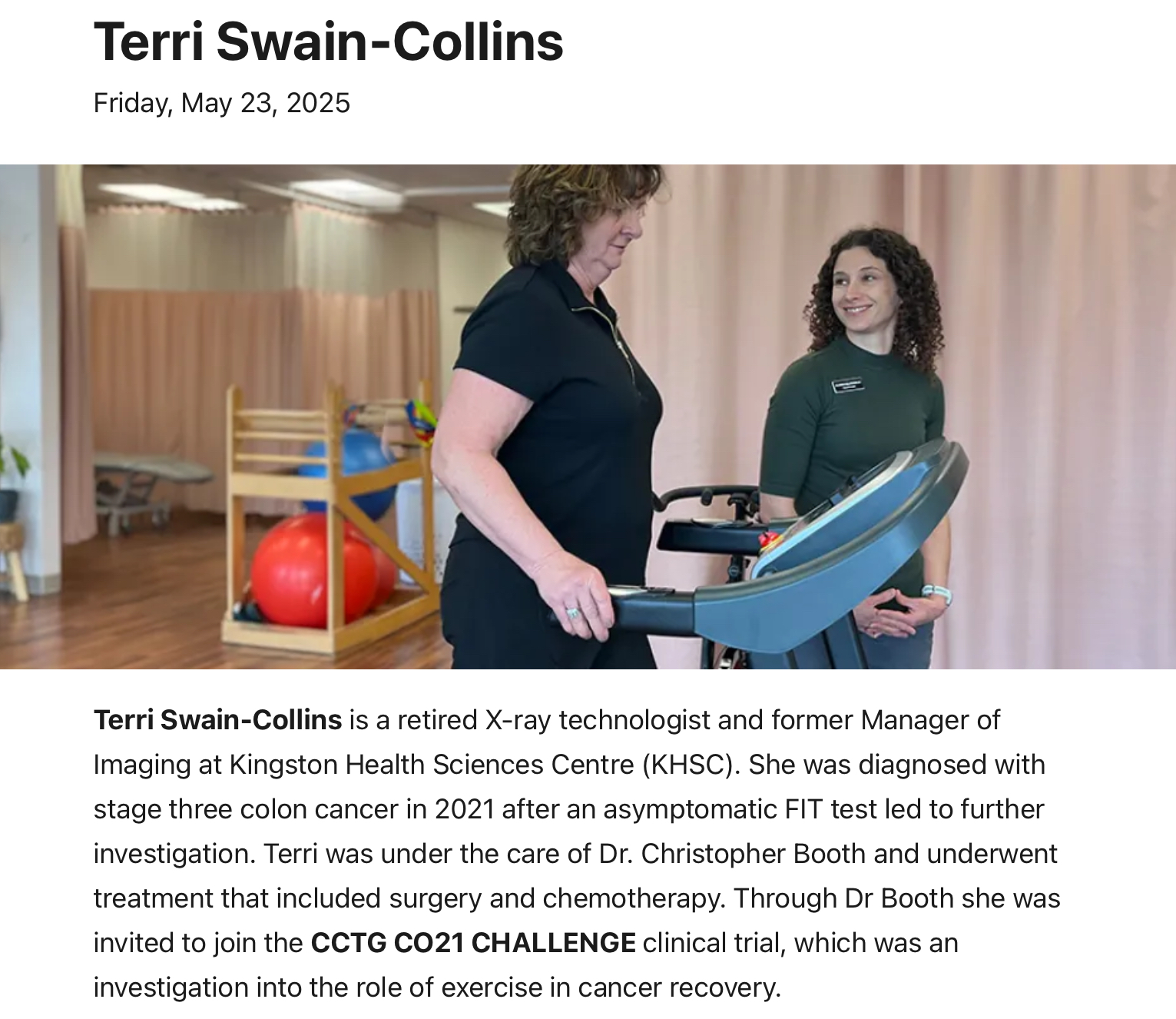

コメント