「便通の回数が減っている」「お腹が張って不快だ」といった悩みを抱えている方は少なくありません。
便秘は、週に3回以下しか排便がない状態を指し、生活の質に大きな影響を及ぼすことがあります。
便秘の原因は人それぞれですが、特に食事の内容や日常の行動が深く関係していることが多いです。
今回の記事では、アメリカ・マウントサイナイ医科大学の消化器病学准教授であるElana Maser医師らの意見を交えながら、便秘に関連する食品や生活習慣について紹介します。
参考記事)
・Behaviors and Foods That Cause Constipation(2024/06/16)
食生活が便秘に与える影響

Elana Maser医師は、「便秘が悪化すると、ほとんどすべての食べ物が悪者のように感じられてしまい、つい制限してしまう傾向がある」と述べています。
しかし、実際には特定の食品だけが便秘を引き起こすわけではなく、食生活全体のバランスやライフスタイルも組み合わさって腸の動きを鈍らせているのです。
便秘を感じた際に過剰に食事制限を行うと、かえって腸内の活動がさらに鈍くなってしまいます。
そういった症状を改善するためには食物繊維や水分を十分に摂取する必要があるというのが現在主流となっている見解です。(Eating, Diet, & Nutrition for Constipationより)
繊維は炭水化物の一種でありながら、体内では消化吸収されず、腸内を通過する過程で便のかさを増やし、排便を促す役割を果たしています。
そのため、食物繊維などの繊維質の食品を十分に摂取することが、最も基本的かつ効果的な対策であると専門家たちは強調しています。
ではそういった食品とは反対に、便秘を招く食事とはどのようなものなのでしょうか。
便秘を招く食品とは?
1. グミキャンディや甘いお菓子

色とりどりのグミやキャンディなどの甘いお菓子は、可愛らしい見た目とは裏腹に、便秘の原因になりやすい食品です。(Association between Dietary Factors and Constipation in Adults Living in Luxembourg and Taking Part in the ORISCAV-LUX 2 Surveyより)
上記のルクセンブルクの成人1558人を対象にした研究では、糖質や塩分の多い食事、およびカロリーが高い食品を摂取しがちな人は、便秘の増加と優位に相関しているという結果が示されました。
これらは繊維が非常に少なく、ゼラチンや砂糖といった成分が腸の動きを鈍くする可能性があるとされています。
Maser医師は「これらの高糖質なキャンディは、最も便秘を引き起こしやすい食品の一つです」と語っており、特にグミを頻繁に食べる一方で、野菜や果物などの繊維を摂取していない場合、腸内の蠕動運動(ぜんどううんどう)が弱まり、便が滞りやすくなると指摘しています。
2. 乳製品

チーズや牛乳といった乳製品もまた、過剰に摂取すると便秘を引き起こすことがあるとされています。(Cow’s milk allergy: evidence-based diagnosis and management for the practitionerより)
特に、牛乳に含まれるカゼインというタンパク質や脂肪分が消化器に負担をかける可能性があるのです。(Milk and dairy products: good or bad for human health? An assessment of the totality of scientific evidenceより)
共同研究者であるProvidence Saint John’s Health CenterのRudolph Bedford医師は、「慢性的な便秘に悩む方には、できる限りアーモンドミルクやオートミルク、豆乳などの植物由来の代替乳製品を勧めています」と述べています。
一方、Maser医師は「乳製品を完全に除去するのは推奨していません」と言及し、ビタミンDなどの栄養素を摂取するためにも、可能であれば食事全体のバランスで調整する方が良いとしています。
3. 加工食品と揚げ物

ファストフードやスナック菓子などの加工食品は脂肪分が多く、繊維が少ないという共通点があります。(Ultra-processed foods and obesity and adiposity parameters among children and adolescents: a systematic reviewより)
こうした食品を常食していると、腸内の動きが悪くなり、結果として便秘を招きます。
その他、肥満や糖尿病、神経疾患との関連性も指摘しされており、摂取すること自体の安全性が疑われています。
4. 赤身肉

赤身肉そのものが便秘を引き起こすわけではありませんが、食事に占める肉の割合が高すぎると、繊維を含む食品の摂取量が自然と減る傾向にあります。
Bedford医師は「赤身肉中心の食生活を送っている人は、野菜や全粒穀物などの摂取量が不足していることが多い」と指摘しています。
行動パターンが与える影響
1. 食生活の急な変化

旅行中や外食が続いたときに便秘になることはよくある話です。
これは、普段とは異なる食材や食事の時間帯が腸内リズムを乱すためです。
Maser医師は「腸は安定したリズムを好む」と述べ、旅行時には日常的に食べている繊維食品(例:朝食のおにぎりなど)を持参するのも一つの方法だと提案しています。
2. 食事量の減少

ダイエットなどで食事量が急激に減ると、腸の働きも鈍くなります。
これは、胃が十分に膨らまないことで「胃結腸反射(gastrocolic reflex)」が起こらなくなるからです。
この反射は、胃が膨らむと同時に大腸の蠕動運動が始まる自然な反応で、排便を促進します。
したがって、たとえ食事制限中であっても、繊維をしっかり含んだ食品を選ぶことが便秘予防につながります。
3. 薬の副作用
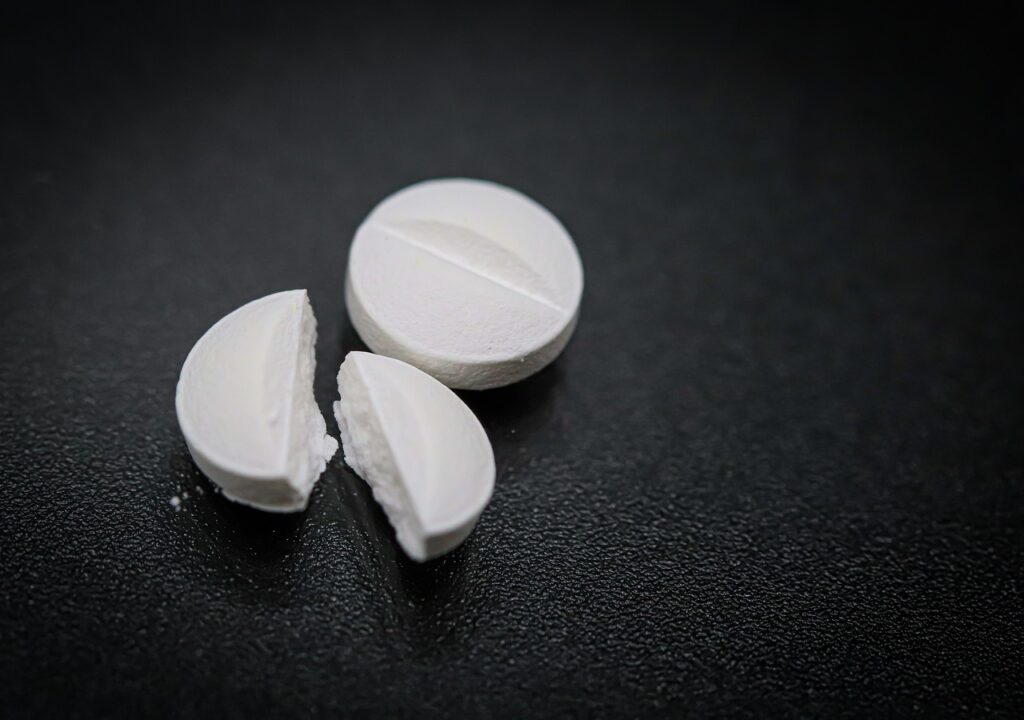
アレルギー薬や胃酸抑制剤、高血圧の薬などが便秘の原因になる場合があります。(Association between Drug Usage and Constipation in the Elderly Population of Greater Western Sydney Australiaより)
Bedford医師によれば、多くの人が薬の副作用を理解せず、便秘解消のために下剤を濫用してしまう傾向があるとのことです。
現在服用している薬がある方は、医師に相談することで副作用に対処しながら継続的な治療が可能になると強調されています。
便秘を予防・改善するためにできること
日常生活の中で便秘を予防・改善する方法として、次のような取り組みが有効とされています。
• 全粒穀物や野菜、果物を多く含む高繊維の食事を意識する
→1日あたり22〜34グラム(g)
• 定期的な運動(週に3~4回のウォーキングや水泳など)を行う
→週に3〜4回以上が理想
• 水分をしっかり補給する
→成人は一般的に体重1kgあたり約35ml
• 便意を感じたときには我慢せずトイレに行く
Eating, Diet, & Nutrition for Constipation
より
まとめ
・便秘の主な原因は、食物繊維の不足と生活習慣の乱れ
・グミキャンディや乳製品、加工食品は便秘を悪化させる可能性がある
・旅行中の食事変化や薬の副作用も、便秘の一因になることがある























コメント