アルコールが健康に与える影響には、私たちが思っている以上に多岐にわたるものがあります。
例えば、二日酔いによる頭痛や不安感といった短期的な症状から、がんのような長期的な健康被害までが含まれます。
近年では、「酒は百薬の長」という言葉とは裏腹に、少量のお酒でも健康に良くないという研究も見られ、禁酒を推奨するような風潮も出てきています。
では、実際にアルコールをやめた場合、どのような身体的・精神的な変化が起こるのでしょうか。
本記事では、オーストラリアのカーティン大学およびUNSWシドニー(ニュー・サウス・ウェールズ大学)が発表した研究に基づき、アルコールを断った後に起こる身体の変化を「1日後」から「1年後」まで時系列に沿って紹介します。
参考記事)
・This Is What Happens to Your Body When You Stop Drinking Alcohol(2025/07/15)
・Quitting Alcohol Can Improve Cognitive Function for People Experiencing Severe Alcohol Use Disorder in Just 18 Days(2022/10/12)
参考研究)
・Association Between Changes in Alcohol Consumption and Cancer Risk(2022/08/24)
アルコールをやめて1日後:すでに変化が始まる
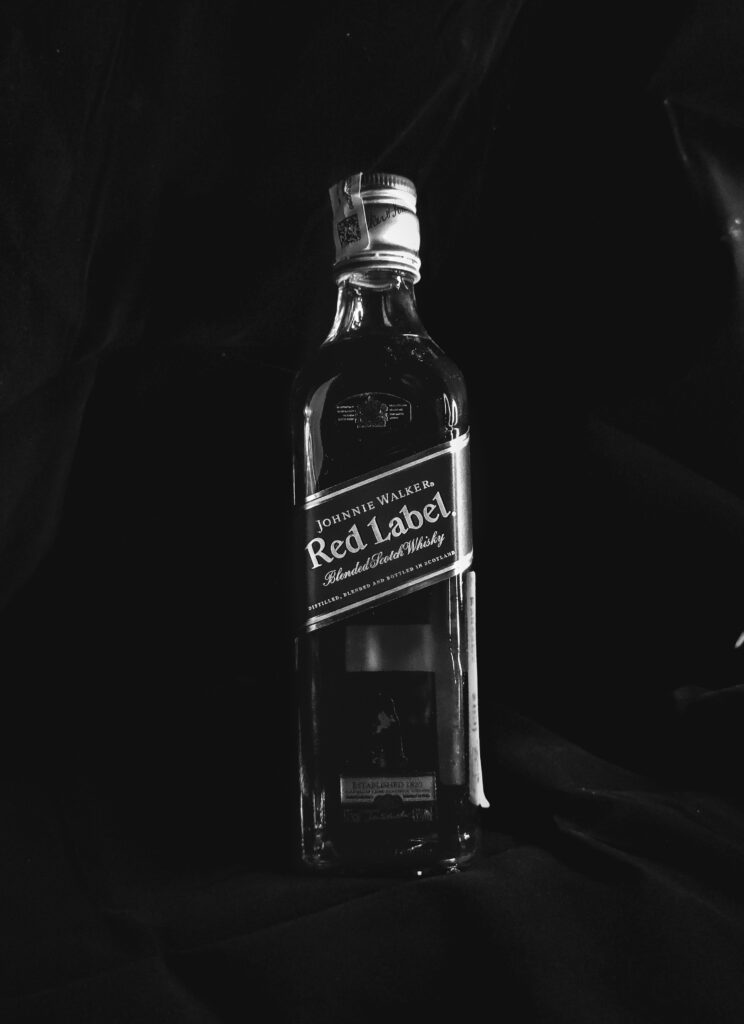
アルコールは摂取後、約24時間以内に体内から完全に排出されるとされ、この段階からすでに身体には良い変化が始まります。
たとえば、アルコールは利尿作用があり、体を脱水状態にします。
しかし、アルコールが抜けることで水分吸収力が回復し、消化機能や脳の働き、エネルギーレベルが向上します。
また、アルコールは肝臓による血糖調整を阻害しますが、体内から抜ければ血糖値も安定しやすくなります。
ただし、日常的に飲酒していた人の場合、アルコールが抜けた初日には逆に気分の落ち込み、不眠、発汗、手の震えなどの離脱症状が現れることがあります。
これらの症状は通常、1週間以内に収まると報告されています。
1週間後:睡眠・肝機能に顕著な改善がみられる
アルコールは一時的に眠気を誘いますが、睡眠サイクルを乱すため、実際には睡眠の質を低下させます。
禁酒1週間を迎える頃には、より深く質の良い睡眠が取れるようになり、朝の目覚めが爽やかになる人が増えます。(Chapter 24 – Alcohol and the sleeping brainより)
また、肝臓はアルコールの解毒を担う重要な臓器であり、軽度でも飲酒によりダメージを受けやすいとされています。
しかし、肝臓は再生能力が高く、禁酒から7日程度で脂肪の蓄積や軽度の組織損傷が回復し始めるという報告もあります。
さらに、少量の飲酒であっても脳機能は一時的に抑制されることが分かっています。
飲酒を中断することで、軽度の飲酒者であれば数日以内に、重度の依存者でも1か月以内に脳機能が回復し始める可能性が示されています。
1か月後:気分の改善、体重減少、腸内環境の回復
数週間から1か月の禁酒を続けると、不安やうつ症状の軽減が顕著に現れます。
多くの人が、気分の安定や精神的な幸福感の向上を実感するようになります。
この時期には、より健康的な食習慣やライフスタイルを選びやすくなり、エネルギーレベルが上昇します。
また、禁酒によって自信がつき、飲酒習慣を見直す意欲が高まる人も多くなります。
アルコールは高カロリーなうえ、食欲を刺激する作用があるため、禁酒を続けることで体重や体脂肪が減少する傾向もみられます。
肌の状態も変化します。
アルコールによる脱水と炎症は肌の老化を促進しますが、禁酒によりその作用が改善されることで、肌のつやが戻り若々しく見えるようになることも示唆されています。
また、アルコールは腸粘膜を刺激し、消化機能に悪影響を与えるため、禁酒することで、膨満感、胸焼け、下痢などの胃腸症状も1か月ほどで軽減することが分かっています。(Alcohol and Gut-Derived Inflammationより)
加えて、禁酒1か月で、インスリン抵抗性(糖尿病の原因となる)が約25%改善し、血圧は約6%低下するというデータもあります。
これは、がんの発症リスクを示す成長因子の低下にもつながり、がんの予防効果も期待されています。(Cancer Growth Factorより)
6か月後:肝臓の回復と感染症への抵抗力向上
禁酒を始めて6か月が経過する頃には、軽度から中程度の肝障害がほぼ完全に回復すると報告されています。(Natural Recovery by the Liver and Other Organs after Chronic Alcohol Useより)
この段階では、免疫力の改善も感じられることがあり、特に以前に飲酒量が多かった人ほど、風邪や感染症にかかりにくくなったという体感があるようです。
また、持続的な禁酒によって、多くの種類の癌になるリスクが低下するとされています。
ソウル大学による研究では、3〜7年間にわたって400万人以上の成人のがんリスクを調べたところ、アルコール関連のがんのリスクは、軽い飲酒((1日に15 g未満のアルコール摂取)をしていた人が禁酒を行った場合、4%低下したことが分かりました。
大量の飲酒(1日に30g以上)をする人が中程度(1日に15g以上30g未満)に減らすことでも、アルコール関連のがんリスクが9%減少することが分かり、さらにアルコール量を減らすと、そのがんリスクはさらに低下することも示唆されています。
1年後以降:慢性疾患リスクの本格的な低下

長期的に見ると、アルコールの摂取は以下のような多くの慢性疾患と深く関連しています。
• 心疾患
• 脳卒中
• 二型糖尿病
• 7種類以上のがん
• 精神疾患(うつ・不安障害など)
しかし、禁酒を継続することで、これらの疾患の発症リスクを確実に低下させることができるとされています。
アルコールはまた、高血圧の大きな要因でもあります。(High blood pressure dangers: Hypertension’s effects on your bodyより)
たった2mmHgの血圧上昇でも、脳卒中による死亡リスクが10%、冠動脈疾患による死亡リスクが7%増加すると報告されています。
アルコールを減らすことで、血圧が下がり、腎臓病、眼疾患、勃起障害のリスクも下がると考えられています。
禁酒のコツとサポート体制
禁酒や減酒には明確な目標設定と段階的な実行計画が効果的です。
また、変化を体感しやすくなるため、体調の変化や気分の変化に意識を向けることが重要です。
1週間、半月とやってみて、身体に起こった良い変化に気づければ、自然とやめていく方向へと向かうでしょう。
また、アルコールによる害などについても学ぶことも、禁酒の動機づけとしては有効です。
もし禁酒に困難を感じている場合は、専門家に相談するのも有効でしょう。
まとめ
・アルコールをやめると、1日目から身体機能が回復し始める
・1か月で睡眠や気分、体重、肌の状態などに明確な変化が現れる
・6か月〜1年の継続により、肝臓や心血管、がんリスクの低下が期待できる
























コメント