マインドフルネスは自宅でも無料で実践できることから、ストレスやメンタルヘルスの改善に効果的な手段として広く推奨されています。
近年では、企業や学校、医療機関でも導入され、メンタルケアの主流の一つとなっています。
しかし、マインドフルネスや瞑想には負の影響があることがあまり語られていません。
実際のところ、古くから伝わる仏教の文献や、現代の科学的研究によって、瞑想による負の影響が確認されています。
本記事では、瞑想の歴史的背景とともに、科学的研究による負の影響の証明、ビジネス化による問題点、子どもへの影響、そして今後の課題について解説します。
参考記事)
・Meditation can be harmful – and can even make mental health problems worse(2024/06/19)
参考研究)
・Prevalence of meditation-related adverse effects in a population-based sample in the United States(2021/06/02)
マインドフルネスの歴史と負の影響
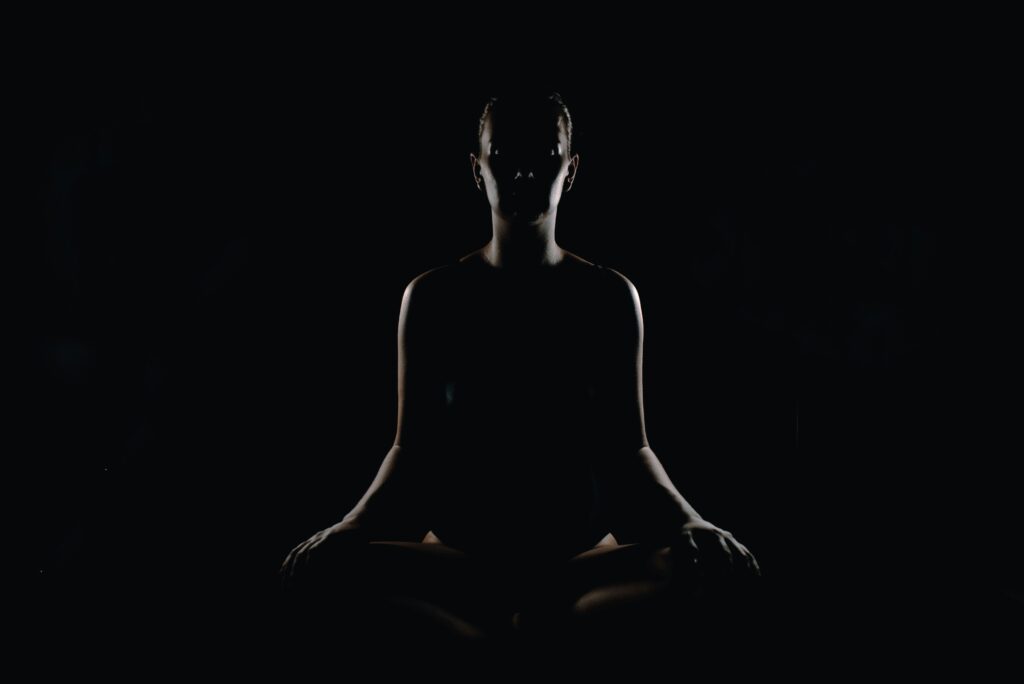
マインドフルネスは、仏教に由来する瞑想法であり、「今この瞬間」に意識を集中させることを目的としています。
これは、呼吸や身体の感覚、思考や感情に注意を向けることで、心の安定を図るものです。
この実践の起源は1500年以上前のインドに遡ります。仏教の瞑想に関する最も古い文献の一つである『Dharmatrāta Meditation Scripture(ダルマトラタ瞑想経典)』には、瞑想後に生じる抑うつや不安の症状についての記録が残されています。
さらに、精神病、解離(自分が現実から切り離されたように感じる状態)、脱人格化(世界が「現実ではない」と感じる状態)といった症状が報告されています。
これらの記録は、現代の心理学や精神医学の視点から見ても、非常に重要なものです。
なぜなら、これらの症状が瞑想による一時的なものではなく、長期間続く可能性があることを示唆しているからです。
科学的研究による負の影響の証明
この8年間で、瞑想の負の影響に関する科学的研究が急増しました。
従来、瞑想は「心を落ち着け、ストレスを軽減するもの」として推奨されてきましたが、近年の研究では、それが必ずしもポジティブな影響ばかりではないことが明らかになっています。
2022年の大規模調査
• 米国の定期的な瞑想実践者953人を対象にした研究では、10%以上の参加者が、日常生活に重大な悪影響を及ぼす症状を経験し、それが1か月以上続いたことが明らかになりました。(Prevalence of meditation-related adverse effects in a population-based sample in the United Statesより)
2020年の40年分の研究レビュー
• 40年以上の研究をまとめた2020年のレビューによると、瞑想による最も一般的な負の影響は「不安」と「抑うつ」でした。
• 次いで、「精神病的・妄想的症状」「解離・脱人格化」「恐怖感」などが報告されていました。
• さらに、過去に精神的な問題を抱えていなかった人々でも、瞑想の中程度の実践で長期的な症状を引き起こす可能性があることが示されています。
(Adverse events in meditation practices and meditation-based therapies: a systematic reviewより)
このような研究結果は、瞑想が必ずしも万人にとって安全な手法ではないことを示唆しています。
西洋における認識の歴史
西洋でも、瞑想の負の影響についての認識は以前から存在していました。
1976年、認知行動科学の重要人物であるArnold Lazarusは、瞑想が無差別に使用されると「抑うつ、興奮、さらには統合失調症の悪化といった深刻な精神医学的問題を引き起こす可能性がある」と警告しました。(Psychiatric Problems Precipitated by Transcendental Meditationより)
しかし、この警告は十分に広まることなく、現在でもマインドフルネスのポジティブな側面ばかりが強調されがちです。
マインドフルネス市場の拡大と問題点
マインドフルネスは、個人の精神的な安定をもたらすとされていますが、そのビジネス化が進む中で、負の影響が軽視される傾向があります。
2023年、管理学教授であり仏教指導者でもあるRonald Purserは、マインドフルネスを「資本主義的スピリチュアリティ」と表現しました。(McMindfulness by Ronald Purser; Mindfulness by Christina Feldman and Willem Kuyken – reviewより)
米国では、瞑想市場は22億ドル(約3200億円)規模に達するとされています。
マインドフルネス業界のいわるゆる指導者と呼ばれるたちは、その問題を知っているはずですが、その点を強調されることはまずありません。
マインドフルネス運動の主要人物であるJon Kabat-Zinnは、2017年のインタビューで「マインドフルネスのポジティブな影響に関する研究の90%は質が低い」と認めています。(Master of mindfulness, Jon Kabat-Zinn: ‘People are losing their minds. That is what we need to wake up toより)
また、瞑想の負の影響は、子どもにも及ぶ可能性があります。
2016年から2018年にかけて、英国の84の学校で8,000人以上の子ども(11~14歳)を対象に行われた大規模研究(総額800万ドルの費用)では、マインドフルネスが子どもの精神的幸福を向上させなかっただけでなく、メンタルヘルスのリスクがある子どもには悪影響を及ぼす可能性があることが示されました。(School-based mindfulness training in early adolescence: what works, for whom and how in the MYRIAD trial?より)
しかし、この研究はメディアでほとんど報道されなかったことも、商業的な意図が絡んでいると疑われても仕方ありません。
これら研究のレビューから、瞑想の実践が精神的な健康を向上させる可能性がある一方で、その負の影響についても十分な注意を払う必要があると言えます。
安全に瞑想を実践するための研究はまだ始まったばかりであり、法的拘束力のある明確なガイドラインが存在しません。
指導者が瞑想やマインドフルネスを指導する際には、その負の影響についても明確に伝えることが倫理的に求められる一方、実践する側には、そのメリットとデメリットを考える必要があるでしょう。
まとめ
・瞑想やマインドフルネスには、不安や抑うつ、解離などの負の影響があることが科学的に証明されている
・ビジネス化が進む中で、マインドフルネスの負の側面が十分に伝えられていない
・安全な実践方法を確立し、指導者が負の影響について適切に対応することが求められる























コメント