【前回記事】
この記事では、中華戦国時代末期(紀元前403~紀元前222年頃)の法家である“韓非”の著書“韓非子”についてまとめていきます。
韓非自身も彼の書も、法家思想を大成させたとして評価され、現代においても上に立つ者の教訓として学ぶことが多くあります。
そんな韓非子から本文を抜粋し、ためになるであろう考え方を解釈とともに記していきます。
【本文】と【解釈】に分けていますが、基本的に解釈を読めば内容を把握できるようにしています。
今回のテーマは“世の事を論じ、因(よ)りて之が備えを為す”です。

世の事を論じ、因りて之が備えを為す
【本文】
上古(じょうこ)の世は、人民少なくして禽獣(きんじゅう)衆(おお)く、人民、禽獣虫蛇(きんじゅうちゅうだ)に勝たず。
聖人作(おこ)る有りて、木を構えて巣を為(つく)り、以て群害を避く。
而(しこう)して民之(これ)を悦(よろこ)び、天下に王たらしむ。
之を号して有巣氏(ゆうそうし)と曰(い)う。
民、果蓏(から)・蜯蛤(ほうごう)・腥臊(せいそう)・悪臭を喰らいて、腹胃を傷害し、民、疾病多し。
聖人作(おこ)る有りて、燧(すい)を危りて鑚(き)りて火を取り、以て腥臊を化す。
而して民之を説(よろこ)び、天下に王たらしむ。
之を号して燧人氏と曰う。
中古の世、天下大水あり、而して必ず鯀(こん)・禹(う)、瀆(とく)を決す。
近古の世、桀(けつ)・紂暴乱なり、而して湯(とう)・武征伐(せいばい)す。
今夏后氏の世に搆木鑚燧(こうぼくさんすい)するある者有らば、必ず鯀・禹に笑われん。
殷、周の世に決瀆(けっとく)する者有らば、必ず湯・武に笑われん。
然らば則(すなわ)ち今、尭・舜・禹・湯・武の道を当今の世に美とする者有らば、必ず新聖に笑われん。
是(ここ)を以て聖人は修古を期せず、常行(じょうこう)に法(のっと)らず、世の事を論じ、因(よ)りて之が備えを為す。
【解釈】
太古の世は、人よりも鳥獣などの獣の方が多く、人はそういった獣や虫には勝てなかった。
そこで聖人が現れ、木の上に住み家を作るよう工夫し、獣たちによる害を避けた。
人々はこの聖人に喜び服し、王としてまつり上げ、彼を有巣氏と呼んだ。
しかし、まだ人は木の実、草の実、貝、獣や魚など血生臭いのを生で食べ、そのために胃や腸を壊し、病気になる者が多かった。
そこで聖人が現れ、火打石を使って火を起こし、血生臭いや木の実を煮焼きし食い良くした。
人々はこの聖人に喜び服し、王としてまつり上げ、彼を燧人氏と呼んだ。
中古の世になって、天下に洪水があった。
そこで鯀(こん)と禹(う)が、(水が氾濫しないよう)所々に堀を作り天下を救った。
また、近古の世には桀王や紂王のような暴君が現れ、圧政を敷いた。
そこで湯や武のような王が立ち上がり征伐した。
もし夏后氏の世に、(聖人として)木の上に住み家を作ったり、火打石で火を立てる者があれば、必ず鯀や禹に笑い飛ばされるだろう。
もし殷や周の世に、堀割りを言い立てる者があれば、必ずや湯や武に笑い飛ばされるだろう。
こういったことから、もし尭・舜・禹・湯・武たちが行った事業をこの現代に言い立てる者がいたなら、必ず現代の聖人に笑われるだろう。
だから、聖人という者は古代の道を倣(なら)い修めることを目的とせず、常則にのっとらず、現在の世に重要な事は何であるかを問題にし、それに対して必要な対策を立てるのである。
その時代に適した考え方を持つべし
有巣氏から樹上に住み家を作ることを学び、燧人氏が火を使うことを学び、鯀と禹から治水を学んだ。
暴君による圧政時には、湯王や武王が現れ成敗した。
これらはそれぞれの時代に適したものであり、もし時代が移り変わっても同じことをしていたら、その時代の聖人たちに笑われてしまう……と韓非は述べています。
過去の成功例や取り決めだからといって、今の社会情勢を考えず、同じ考えにしがみついていてはいけないということですね。
自分としても、これからの新しい時代にいつでも対応できるよう情報を取り入れ、柔軟に対処できるよう準備していきたいところです。
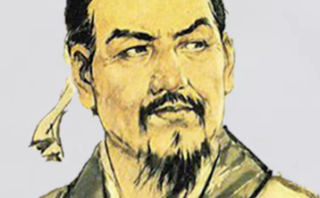
コメント